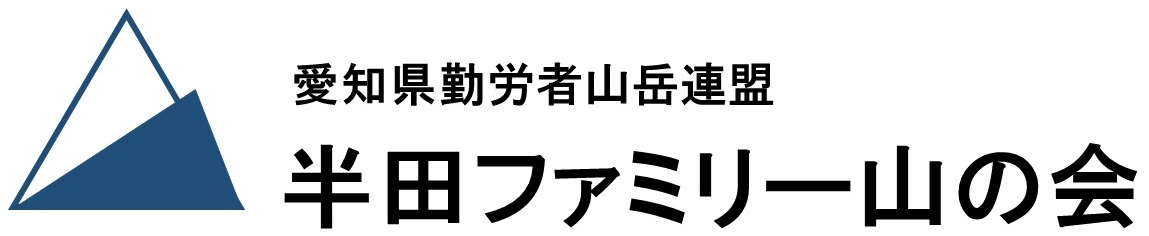洞井 孝雄
アメリカでは大統領選が過熱しています。国内では、自民党の総裁選、立憲民主党の代表争いが、毎日取り沙汰されています。武田砂鉄さんがコラムで、“自民党総裁に出馬した9人は、曖昧なまま逃げ回っている裏金議員たちについて問われると、曖昧に応える。曖昧な人たちの処理を曖昧に述べるので、どんどん曖昧になり、薄まっていく。もちろん、そうやって薄めるのが目的なのだが、薄めておきながら、ひとまず強気なのが奇妙だ”、“会見に挑む候補者の背後に刻まれていたスローガンは、「今はこんな感じかと残念に思われているかもしれないけれど」という共通した前振りで、「決着 新時代の扉をあける」「自民党は生まれ変わる。」「国民と向き合う心、世界と渡り合う力。」「日本の新しい景色」など、自分が新総裁・首相になったら、これまでとは違う、新しい政治が誕生すると訴えている。”と述べています。今まで何をやってきたの? 裏金問題をはっきりさせるのが先じゃないの?、とい武田さんの思いがよくわかります。同感。世界の将来も日本の将来も心配だなぁ。
パラリンピックが終わりました。報道では、選手たちの健闘やフランスのパラリンピックへの関心の高さが伝えられただけでなく、日本ほど施設はバリアフリー化されていないけれど、パリでは、随所で障害者たちの手助けをしようとする市民の意識の高さも伝えられていました。こういうところはきちんと見習いたいものです。
ドジャースの大谷くんが打つたび、走るたびに記録が更新されていきますが、大台に乗るまであとちょっと、というところで少し速度が鈍ってきているようです。相手チームも、自分の対戦のところで記録更新させてなるものか、と必死に向かってくるわけですから、そう簡単には行きません。でも、50-50、やってほしいですね。今、48-49です。
新関脇の大の里が11連勝。この『もみのき』が出たときには賜杯を抱いた後かも知れませんが、彼だけではなく、同世代の力士の競い合い、こちらも楽しみです。
さて、8月から9月にかけて、たくさんの登山計画が提出されました。天候不順や、9月上旬の居座り台風のおかげで、中止や変更を余儀なくされたことも手伝ってか、9月の二週連続の連休に結構アルプスに向かう計画が出されているような感じを受けました。今年の夏山後半(7月25日~8月26日)は、長野県北アルプスでの遭難が特に多かった(近郊低山は不明)とのこと、最終的にはどうだったのでしょうか、安全に良い登山ができていればいいのですが。報告を待ちましょう。
私自身は、うだるような暑さと、混雑しそうなあちこちのメジャーな山へは食指が動かず、休日を避けてウイークデイに一二度、近郊の山に行ったのと定例山行に参加しただけでしたが、登れば登ったで、それなりに自分の中に残るものがあります。
先月は「やぶマン」500回で、今年の夏合宿を振り返るのと、40年以上も連載してきたことを振り返る二つの内容で書いてみました。これからどうしようか、一つ区切りがついたので、もうそろそろいいかな、と思ってもいたのですが、まあ、ネタがあるウチは、力尽きるか、「もうええわ」と言われるまでは続けようかな、とも思ったりします。今月の501回目、初心に還るつもりで、「自分が登山を続けている理由、について考えてみたい、と思います。
体力テストとトレーニング
9月の教育セミナーは「体力トレーニング」でした。簡単な体力テストも行われましたね。
『もみのき』510号(7月号)の「やぶマン」№499に「筋力を鍛える」と題して鹿屋体育大学名誉教授の山本さんの講義の報告をした後だったので、私自身も面白がって参加させて貰いました。体力テストには、会員の皆さんも真剣に(やっぱり競争意識が働くのでしょうね。みんな往生際悪くじたばたしていました)取り組んでいた姿が思い出されます。
この「やぶマン」で報告した内容が正確かどうかを見ていただこうと、『もみのき』510号と、あわせて、あの体力テストの結果(教育部長がデータをまとめてくれました)を、山本さんにお送りしました。
山本さんからは、「私の言いたいことはすべて網羅されている」という丁寧な返事をいただきました。あわせて、「軽登山を励行している70代の女性会員はしっかり歩けているというコメントには、私の方でも我が意を得たりの心境で、軽登山を推奨することにさらに自信が持てました。後はできる範囲で、少しずつ筋トレやエクスハイクを加えていくことで、さらによい結果が出てくるのではないかと思います」というアドバイスもいただきました。
また、体力テストについては、「傾向としてはよい成績」で、立ち上がり(脚筋力)、状態起こし(腹筋力)のような筋力系の能力が(特に女性で)高いこともよいことで、このようなテストを時々やることは、自分の体力に目を向けるよい機会になる、とも。
ただ、これらのテストは、「下界で普通の生活をしている人用の体力テスト」なので、「この体力がそのまま山で通用するわけではない」ということにも注意して欲しい、ということでした。登山をする人は一般人に比べて確かに筋力は強いが、それだけでは安全な登山ができるレベルには届かない、と言うことです。
また持久力のテストの方法についてもお尋ねしましたが、これらについては、自身の考案された筋力テストや、実際の山でマイペース登高能力テストを参照して欲しいこと、会でもチャンスがあればやってみて、様子を聞かせて欲しい、ということでした。
登山者用の体力テストや筋力テスト、持久力テストについては、私も以前から紹介している『登山の運動生理学・トレーニング学』(山本正嘉著、東京新聞)の中のP49~51,P407、P288~290、P314~317を参照してください。これを受けて、教育部で、これから具体化されていくと嬉しいですね。
「やぶマン」や「体力テスト」の結果から、先日の運営委員会では、教育部から低山トレーニングの取り入れ方やその考え方、実施方法などについて、腹案が出されました。私たちの会で、もっともいい方法での実施ルールを考えていこう、ということになりました。近々に、トレーニングのための山行について、提案されることになるだろうと思います。
なぜトレーニングしてまで登山を
さて、前置きが長くなりました。トレーニングや体力テストを前振りにしたのは、これらが、「山に登る」ためにおこなっているわけですが、では、「山に登る」ということのために、なぜ、私たちは、こんなエネルギーを費やしているのか、「なぜ、山に登るか?」ということではなくて、自分たちひとりひとりの、「なぜ、山に登っているのか?」(その理由はひとりひとり違う)、そのために、どうして、こんな体力トレーニングをしてまで登ろうとするのか、その理由、言い換えれば一人一人にとっての「自分が登山する理由」というものを考えて貰うきっかけにしたいと思ったからです。
昨年は『もみのき』500号、先月は「やぶマン」500回、その節目に原稿を書くとき、やはり、これまで自分が書いてきたものや、機関紙・誌のバックナンバーを取り出して目を通すことが多かったからかもしれませんが、登山の回数、山域、そこでの登山体験、できごと、同行者、山の状況や環境、そういったものを、昨今の機関紙・誌の報告と見比べて、いったい、どう思っているんだろう、と思うことがよくあるのが、会の仲間たちの山行です。
昨今の山行報告。登山の意味は…
なぜ、山なんかに登っているのか、という理由には正解なんかはないし、一人一人違うわけですから、他人のことなんかいいじゃないか、と思いつつも、登った、ということと、ともすれば時間の羅列だけで、登山ルートのポイントや地形の特徴もなにもわからない「記録」、自分だけにしかわからない数行の「感想」、荒っぽいPCで線を引いた「概念図」だけで構成された山行報告を見ると、その山行は、どんなところをどうやって登ったか、そのひとにとって、どんな意味があったのか、をあまり感じられないなぁ、と思ってしまうこともしばしばです。
今と昔、比較にならないくらい
どこかで書いたことがあるのですが、会が発足した当時の機関紙・誌には、山行記録はもちろんですが、それよりも、自分たちが持っている山への憧憬や登山に対する思い、会の中での会員同士のつながり(考え方や意見の違いや絡み合い)みたいなものが率直に表現されていたように思います。現在のように、週休二日制になったり、ずっと休みが取りやすくなって、週末でもウイーク・デイでも時間はとれるし、情報はネットを検索すればほとんど無尽蔵と言っていいくらいに手に入り、交通機関も登山環境も随分変化して、コロナ禍以後、山小屋やテント場は予約が必要になって、反対に山域を制限されるようになったこと以外は、30年40年前とは比べものにならないくらい飛躍的に山行回数が増加しました。月に二回くらい山に入っている仲間が「すごいね」と言われるような時代、年間50日も山行日数を確保していれば、その人をみる目がかわると言うような時代から、毎週、あるいは二週間で三回、年間では50日、60日は当たり前の山行をする人たちの時代へと変わってきました。
それだけに、会員の機関紙・誌の山行報告は、おざなりになり、原稿を集めて機関紙を編集・発行をする側も、回数が多い分だけ、負担を避け、短く、定型的な原稿を歓迎するようになってきているのではないか、と思えちゃったりすることもあります。
『ごんぎつね』№11がない!?
会の事務所の本棚を見ていたら、『ごんぎつね』の№11が欠けていました。誰からも(編集部からも)指摘がないので、見返したり、読みたいなんて思わないのだろうな、と思うのですが、この『ごんぎつね』第11号は、1995年12月に発行され、会創立15周年の位置づけがされた号です。数えるほどしか残っていない古い会員以外、知らない人の方が多いと思いますが、巻末に、この年の8月に行ったマッターホルン登攀の記録が収められています。この機関誌は、山岳雑誌(確か『岳人』『山と渓谷』『山と仲間』の三誌ともに)に紹介され、「これほど詳細なマッターホルンの登攀記録はない」という評価で、外部からも頒布希望者があったと記憶しています。
会員と一緒に、一年近く準備をしてきたこのマッターホルン登攀の取り組みは、メンバーにとっても、私にとっても大事な山行でした。いま読み返してみると、現在では、現地の状況や環境も、到底こんな山行ができる条件ではなくなっているし、その時代にしかできなかった経験ができた私たちは、大変に幸運だったと思えます。それは、かけがえのない機会であり、大きな値打ちを持つものであったように思えるのです。(№11は、探して、会の本棚に入れておこうと思います。事務所に来たときに目に入ったら、是非、手に取って、読んでください。メンバーたちの山行前後のレポートも傑作だと思います。会に入ってきた当初、山行報告を三行しか書けなかった仲間が、山行後、A4用紙40ページにびっしり40枚以上のレポートを書いてきた、というエピソードが、この登山のインパクトの強さを物語っているとは思いませんか?
50年前の山行記録
自慢話と一緒くたにされてしまっていることが多いのですが、よく、「古い話や思い出話は聞きたくない」という人がいます。
私の登山事始めは、1974年だったか75年だったかに、9月上旬、友人に連れられて、北アルプスの立山から欅平までを縦走したことでした。しばらく前に本棚を整理していたら、その50年ほど前の初めての登山の記録がそのまま出てきました。ガイドブックのコピーの裏に時間の記録と出来事を詳細に書き付けたもので、よく残っていたなと我ながらびっくりしたのですが、国鉄(!)で名古屋を発ち、立山~大日岳、室堂~剣岳~選任湯~水平歩道~欅平まで、汗で擦れた紙とインクのにじんだ記録が、あのときの山の匂いを思い出させてくれました。当時の山と山小屋の状態の空気は、多分、今では絶対にないもののように思います。そういったものを、一つ一つ感じながら、蓄積してきた経験が、今の自分の山登りを作っているといえます。
後追いの知識だったのですが、この初めて歩いた山域が、どんな歴史を持った山域であったかを、後日読んだ書物で知って、「そうか、俺はこんなところを歩いてきたのか」と、その自然の猛威に気づかされ、そのなかで苦闘してきた人間の営みを知って、自分の歩いてきたルートの値打ちを再確認したり、と単に歩くこと以外に、深く山の世界に分け入っていくことになりました。以後、冬の御岳の遭難事故に年を跨いで関わったり、その事故報告書をまとめる作業に加わったり、この捜索を通して知り合った仲間に岩登りの手ほどきを受け、上高地~前穂~奥穂~北穂と一日で縦走し、取りついた滝谷で、仲間が落石を受けて負傷した事故に遭い、ヘリの要請やビバークサイトの撤収や事故の後処理をしたり、と、さまざまな経験の中で、自分の登山の意味を改めて考えさせられたりもしました。
まだ、どこの山岳会にも所属しておらず、半田ファミリーが影も形もなかった頃の私の手探りの登山の時代でしたが、あの最初の北アルプスの縦走以来、記録をつけることが習慣になったおかげで、当時の山の状況を思い返すことができます。当時の空気や匂いは表現できていないので、それらを伝えたり、現状がどのように成り立っているのかを知ってもらうために「昔話」をすることになってしまうのですが、それも自分のくぐり抜けてきた時代の、自分にとっての登山のありようだと思いますし、残しておくのは私たちの役割だと思っています。
自分の登山の理由を
愛知県連所属の山岳会に入り、全国や県連盟の役員を務めながら半田ファミリー山の会の発足以後の登山活動のほとんどは機関紙・誌に書いてきましたが、それらは『ごんぎつね』№11のように、自分にとっては大事な登山の記録であっても、なければないで、誰もそれがなくなったことに気づくこともない自己満足の世界にすぎません。かつてのように口角泡を飛ばして「自分の山を熱く語」り、山に登る時間が貴重で、ひとつひとつの山行が愛おしく、大切に登りながら自分の理想の山登りを追求していく時代ではなくなってしまいました。
でも、できる限り、自分が山に登りたい理由を考えながら登ることが大事ではないか、と思っています。頭も鍛えたいですね。