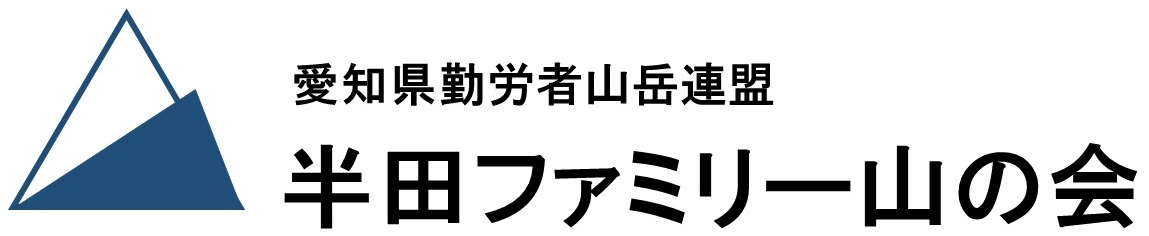洞井 孝雄
先日、セブンイレブンでコーヒーを買ったら、いつの間にか110円になっていておどろきました。さまざまなものが値上がりしつつあります。いや、もっと前から値上がりは始まっていて、これからもっと進んでいくことになるのでしょうが、こんなところで実感するとは。
世界の動きもアジアの動静も、国内の政治も、腹の立つことが多いですね。安倍元首相の国葬の閣議決定、自民党と統一教会との癒着、コロナ感染拡大の第七波への対応の遅さ、物価高騰への無為無策、シレッとした顔で、改憲や軍備拡大を進める岸田首相の支持率低下は十分理由のあることなのでしょう。世界で唯一の被爆国でありながら核禁止条約にも加わろうともしない国で、そのことを厳しく指弾し続けてきたヒロシマやナガサキのひとたちのことを考えると、6日も、9日も、15日も、新聞やTVの報道も、なんとなく空疎で、今年はあまり心に響いて来ませんでした。
夏合宿が終わりました。といっても、もう何週間か前の話。
今年は、いつもならセミの大合唱がやかましくて寝ていられないくらいなのに、今年はそれ程の大音量で鳴きませんでした。合宿が終わってから、お盆のバタバタと天候不順、コロナも油断できないし、で、なかなか山も計画通りにはいかず、出さなければならない原稿もちっとも進まず、あまりいつもの夏らしくない夏をなんとなく過ごした感じです。
さて、今年の夏は久しぶりに穂高岳に登りました。ちょっと感慨深かったので、今月の「やぶマン」、思い出話になりますが、穂高岳の登山を振り返ってみます。
今年の夏の穂高岳
7月下旬に、上高地から涸沢、そして穂高岳山荘に泊まって奥穂高岳、前穂高岳を踏んで、岳沢経由で上高地へ、その三日後に会の夏山合宿で、再び上高地から涸沢に入って幕営し、北穂高岳、涸沢岳を踏んで涸沢に戻り、上高地へ下った。
会の三年前の夏山合宿は、南岳から北穂高岳、涸沢岳への縦走計画だったが、北穂高岳まで進んだところで、時間的にもそれから先に進むのは難しいということで撤退。
その翌年はコロナ禍で中止を余儀なくされ、昨年は「合宿を目ざそう」という呼びかけで、合宿を絶やさず、ともかく準備をすすめよう、という取り組みが、北ア・薬師岳の夏山合宿に結実した。最終的に実施できることになっても、テント場の多くが予約制になっていて、予約が難しく、予約不要のテント場のある山域へ、というのが、合宿の山域が薬師岳になった最も大きな理由だったが、一年間のブランク、新しい会員の参加が多い状況では、結果的に適切な山域選択になったと思っている。
それはさておき、今年の合宿も、テント場の確保は大きな問題だったが、涸沢のテント場は予約不要だった。ここをベースにして、北穂高岳や奥穂高岳に登るのはどうだろう、縦走が難しければ、往復も可能だ。涸沢がベースなら、稜線への行動は、ベーシックの装備を担ぐだけで済む、そうしたコースと時間の組み立てを考えて出てきた案だが、奇しくも三年前、北穂でストップした地点から先へ、つなぐ形になった。
初めての穂高岳で落石事故
私が初めて北穂高岳に登ったのは1977年。
三人パーティーで午後、名古屋を発ち、上高地で一泊、早朝から岳沢~前穂高岳~奥穂高岳~涸沢岳を縦走して、北穂高岳の南稜テラスに日暮れ前に着いた。南稜テラスは、滝谷を登るクライマーたちのビバーク地としてよく使われていた。水がないので持ち上げなければならないが、翌朝、B沢やC沢を下降して、登攀ルートに取り付くのにはいい位置にある。
翌早朝、滝谷第三尾根に取りついたあと、落石事故に遭った経験とその顛末は何度かどこかに書いた覚えがある。
事故の経験はもちろん、初めての穂高岳が滝谷の登攀だったこと、そのアプローチが前穂から北穂への一日での縦走だったことは忘れられない。二日で穂高の稜線を縦走し、滝谷の登攀をして帰ってこようという計画は、徹底した軽量化が図られていた。登攀具を除いて、共同装備の幕営具はツェルトのみ。個人の寝具はシュラフカバーのみ。コッフェルは各自のメタ・クッカー、燃料もメタのみ。行動食以外の共同の食料も、水を節約するために、夕食は当時出ていたカップライス(乾燥米の入ったカップに湯を注いで、すぐに湯を棄てて、数分待てばご飯になるもの)、湯は捨てずにクッカーに戻してスープを作った。朝食は行動食を兼ねたジフィーズ(アルファ米に味付けがされた、当時は高級な乾燥食糧)だった。時間と燃料の節約のために、寝る前に水を注いで、パックの口を輪ゴムで留めておき、翌日、おかゆのようになった中身をパックから直接チュウチュウ吸いながら行動するという、今では誰も一緒に登ってはくれないような貧しい食事だったが、当時の私たちにはそれで充分だった。
その後も、登山学校の研修山行で滝谷を登ったり、会でも、夏の槍ヶ岳~北穂高岳(その逆も)の縦走、春には涸沢をベースに、奥穂高岳や北穂高岳の往復なども何度か合宿で取り組んできたが、長い時間が経って、当時、参加したメンバーのほとんどは、今はもう会に残っていない。
涸沢で合流、うな丼の夏合宿
本隊と後発隊とに分け、本隊は槍ヶ岳から北穂高岳まで縦走して涸沢に下り、後発隊は上高地から登って来て涸沢で合流、という夏合宿を組んだことがあった。
後発隊が担ぎ上げてくれたウナギの白焼にタレをつけてかば焼きにし、全員でうな丼で乾杯したときのことをよく覚えている。
翌日は全員でザイテングラードから穂高岳山荘に上がり、奥穂高岳を往復して、白出のコルから下山した。
山荘のすぐ上のハシゴの登り下りでロープを出しての確保や、白出沢の下りでは、河岸をへつる部分にロープを固定し、プル―ジックで通過した場面などを思い出す。
春の北穂沢、ザイテングラード
春の合宿では、涸沢から雪の北穂沢を登ったことが何度もある。
初めて登る仲間たちがテントから出て、鈍い銀色に光る急斜面を見て、「ほんとうにあそこを登るんですか?」と聞いてきたときの表情を思い出す。雪の付き具合、凍り具合で、年によっては、簡単に登れてしまったり、難しかったりするが、途中、休憩できるような場所がなく、休まずに登り続けたことも忘れられない。
同様に奥穂高岳を往復した春合宿も何度かある。
涸沢からザイテングラードを白出のコルまで(穂高岳山荘まで)何度も登っているのに、あまり苦労して登った覚えがない。雪で埋まってしまった岩稜帯は急な雪面になってしまって、そこを上り下りした記憶だけが鮮明だったので、今年、久々に雪のないザイテングラードをたどってみて、けっこう厳しい場所だったことを思い出した。
穂高岳山荘からは一気に登山道へせり上がる岩場をハシゴで登って行くのだが、シーズンも早いうちに取りつくときには、雪面にトレールがない場合や、多くの登山者が集中する時期によっては大渋滞、という時もある。雪の付き方によっては、渋滞を避けて、ハシゴの脇の雪の斜面を登って、上からロープで確保したこともあった。それはケースバイケースだが、そういう状況を読まずに、しゃにむに人を押しのけるようにしてハシゴ脇を登って落石を起こすパーティーもあって、彼らを怒鳴りつけたこともある。奥穂までの途中で、県連の他の会の仲間が一人で歩いているのと出合い、パーティーがばらけて、ひとりになってしまったのだ、という話を聞いたこともある。けっこう、たいへんな問題だと思うのだが、「ウチの会はいつもこんなですよ」と言われて、またびっくり。何かが起きないと、その怖さや危険は認識できないのかも知れないな、と思ったことだった。
ある時は、ハシゴの直下まで登ったのだけれど、雪の付き方や凍り方を見て、そのまま引き返したこともある。
岳沢、奥明神沢から前穂高岳
他の山岳会と合同で春合宿を取り組んだことがある。会で初めて春山合宿で前穂高岳を目ざしたときのことだ。幸いに、天候も安定しており、積雪量も多くも少なくもなかった。奥明神沢を登って、全員が山頂に立ち、無事に下山してきたのだが、平均年齢も若く、いい条件のもとで、すんなり登って下ってきたことだけが残っている。
その後も何度か、岳沢からの前穂高岳の春合宿を組んだが、登れたときも、天候に阻まれて、岳沢でテントを張っただけで翌日引き返してきたこともある。
ある時は、献立がビーフシチューに決まり、食担になった仲間が、レトルトパックのビーフシチューを買い集め、家族で試食をしたが、持ってきたのは、まだ試食をしていないパックだった、何のための試食だったのだ、という笑い話のようなエピソードもこの前穂の合宿の時のことである。
秋に、明神岳主稜を登り、前穂高岳を経て、岳沢に下るという山行をした。
岳沢に向かう途中から明神岳主稜への踏み跡をたどり、明神岳直下で幕営、翌日、強風の山頂から前穂高岳へ向かったのだが、途中で踏み跡を見失い、前穂高岳の西側の斜面を行ったり来たりしながら前穂高岳の山頂に着いたこともある。
今年、前穂から岳沢へ下るときに、それとなく既視感のある斜面を見ながら、ああ、あの時はこの紀美子平の下部で登山道を外して、あのあたりを行きつ戻りつして上にあがってきたんだったな、などと考えていたのだが、雪のない穂高の岩稜帯も、何度来ても新しい表情を見せてくれる。
ゴジラの背中。割りばし一本でも
夏のある時は、北穂沢の途中から雪面をトラバースし、東稜の登攀をしたこともある。合宿に参加するメンバーの中に、岩登りをするメンバーが一定数いることから、ゴジラの背中と呼ばれる岩稜帯を登るパーティーを編成したのだったが、岩登りよりも、取り付きまでの雪渓のトラバースが課題になった。登攀具の用意はあっても、雪渓のトラバースの想定がなく、ストックもアイゼンもなかったのだ。
「割りばし一本でも欲しい、という時ありますものね」
実際に体重を支えてくれるわけでも、実効性があるわけでもないけれど、微妙にバランスを必要とする場合に、ホンのちょっと手を置く支えが欲しい、この時のことを報告した県連の遭対報告会議で、他の会のメンバーからこう声をかけられたのだが、この言葉は、この時の思いを代弁してくれたものとして、記憶に残っている。
涸沢岳の厳しさ
三年前の夏合宿は、槍平から登って、南岳の「天空の稜線」をみんなで登って欲しい、と考えて、山域をイチ押ししたのだったが、北穂高岳まで随分時間がかかって、その先へ進むのを断念し、北穂のテント場で幕営、翌日はそのまま涸沢へ下って、帰ってきたのだった。
今年は、北穂高岳から涸沢岳を踏んで奥穂高岳へ向かうことが目標(目的ではなく)だったが、これまた、記憶にある北穂から涸沢岳へのルートよりもかなりグレードの高い縦走路だったことを改めて思った。岩は記憶よりも落ち着いていて、浮石やガラガラの部分はほとんどなかったが、岩の間の踏み跡は狭く、急な上り下りと岩のピークが連続して現れ、更に谷側は切れ落ちていて、高いところが苦手な人は、心臓によろしくない。鎖場やハシゴ場も多い。
2011年の夏合宿は、早月尾根から剱岳に登ったが、初日の早月小屋で幕営中に、県連の仲間が、落石事故で亡くなったという連絡を受けた。その事故はまさにこの縦走路で、ハシゴ場の順番待ちをしているときに、他の登山者が落とした石を受け、数十メートル転落して死亡という事故だった。
あとで思ったことだが、三年前に、あのまま北穂高岳で止まらず、先へ進んでいたら、パーティー全体がかなり疲れていたので、ちょっと厳しい状況になっていたかも知れなかった。天候にも恵まれ、比較的早い時間に北穂~涸沢岳間を歩けたのはよかった、と思う。
話が前後するが、今年の合宿の時期には、涸沢ヒュッテで、新型コロナウイルスの陽性患者が出て、私たちが合宿に出発するしばらく前から、私たちが下山した数日後まで休業という状態になっており、上高地もそうだったのだが、横尾から涸沢への登山道も、涸沢のテント場も、涸沢を取り囲む穂高岳の縦走路も、これが、この時期の、この山域か、と思うほどに登山者の姿も少なかった。幸か不幸か、私たちが涸沢を出て、涸沢に下ってくる間、出合った登山者、行き合った登山者も数えるほどで、順番待ちや、私たちが渋滞の元になるようなことも皆無だったのはありがたかった。
帝国ホテルでランチを
会の合宿では、まだ歩いていないルートがある。奥穂~西穂の間だ。
会ができる前、初冬の東海山岳会の仲間二人と西穂高岳から奥穂高岳を縦走した。降った雪が、頭上の岩の上からさらさらと流れ落ちてくるような天気だったが、ジャンダルムを越え、奥穂から白出のコル、涸沢を抜け、夜の横尾まで走り下った。
天狗のコルに二三人用のテントを張った時には、テントだけでスペースはいっぱいで、四囲にロープを張って落ちない用心をしたが、夜中にテントの周りを歩く足音を聞いた。そんなはずはないのだが、他の二人も同じように「聞いた」と口をそろえたのはちょっと不思議な出来事だった。
無雪期に穂高岳山荘のテント場で幕営し、奥穂高岳~ジャンダルムを越えて西穂高岳まで縦走したことも何度かある。
夏、昼前に西穂山荘に着き、今からなら帝国ホテルのランチタイムに間に合う、と上高地へ下った時のことが印象深い。
汗まみれの衣類と泥のついた登山靴姿でレストランに駈け込んだにもかかわらず、丁重に席に案内された。さすが、であった。
メニューはイワナのムニエルだったことを覚えている。
終わりに
久しぶりに穂高岳に足を向けたので、思いつくままに印象深い山行を振り返ってみた。まだまだたくさんの出来事がある。足繁くというわけではないが、けっこう何度か通っている山域だったことに気づいて驚いた。あと何度、登れるだろうか。
(2022.8.31)