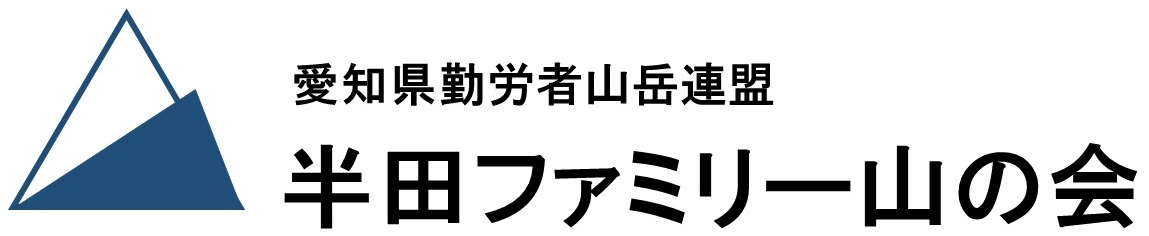洞井 孝雄
統一地方選挙の後半戦の真っただ中(あと数日で終わりです)。前半戦では維新が関西で大勝、大阪にカジノを作る動きが加速しました。後半戦の応援演説に入ろうとしていた岸田首相が襲撃されました。容疑者の動機解明はこれからですが、昨年も同じような事件があったことを思い出させます。今の政権や施策にいっぱい不満があったとしても、人の命を奪おうとする行為は到底許されるものではありません。昨年は、安倍元首相が亡くなり、それまで隠されていた旧統一教会との関係やタブーとされていた様々な事柄が次々と明るみに出てきました。連日、軍拡、増税、学術会議問題、健康保険法改悪、入管法改正、原電の再稼働審査資料、省庁OBの人事介入、自衛隊ヘリコプター墜落、スーダンへの自衛隊機派遣決定など、さまざまな出来事が報道されています。ドイツでは15日、国内すべての原子力発電所の稼働が停止しました。ロシア軍とウクライナ軍の攻防はエスカレート、中国が多くの国に警察拠点を設けているとされ、ますます米中間の摩擦が強まっています。北朝鮮のミサイル発射も相変わらず。あ世界の動き、特にアジア情勢から目が離せません。
会では、春山合宿の取り組みが進んでいます。先日は県連の春山合宿遭対連絡会議が開かれました。私たちの会からは、雪組と花組、ふたつの計画書が提出され、それぞれのパーティーのリーダーが出席して計画の概要を報告しました。
出席してくれたリーダーからは、戻って来て多分「会の合宿の計画には指摘はなかった」という報告がなされることだと思いますが、計画に問題があったかなかったか、という単純な問題だけでなく、各山岳会の合宿の取り組みは、コロナ禍で中断して以後、低調なままの状態が続いており、限られたいくつかの山岳会から計画書がでてきただけ、という状況は何によるものか、他の山岳会との計画書の比較、合宿の考え方捉え方の違いや、パーティーの山行目的、会としての合宿の位置づけの有無、私たちの会の立ち位置などそれら背景も合わせて報告してもらいたいものだ、と思っています。
遭対連絡会議は、出席した各会の担当者がお互いに計画書をつつきあい、疑問点などを明らかにし、山域の新しい情報なども共有するという役割を持っているのですが、昨今のように合宿に取り組む山岳会が少なく、閉塞した山域の状況では、なかなかそういう役割も果たすことが難しくなってきます。こんなときだからこそ、行ける人たちが行きたい山域にパーティーを組んで出かける、ということではなく、会としての合宿の位置づけがどのようなもので、どのように実施されているか、ということが、より大切になってくると思うのです。
今回の「やぶマン」、春合宿について考えてみます。
第43期春合宿。雪組と花組
会の定期総会が終わって、新しい年度の活動が始まった。
この時期の大きな取り組みと言えば、春合宿である。ひと月あまりの準備を経て、仲間たちが残雪の、あるいは新緑の山に向かうのも間もなくである。
会が発足してから1992年まで、春合宿といえば、「残雪期の山」が山域だった。会ができて10年以上も経つと、会員数も会員の登山志向も登山形態も多様化し、それまで登山の世界の「春」山は、残雪期のそれを指していたものだが、同じ会の中で、雪の山に入らない(登山志向、要求、装備・技術の有無etc.・・・)会員も増えて、「雪山の装備や技術もない」、「雪山に行きたいわけではないので、春合宿にはエントリーしない」、「でも合宿をやっている期間は私たちも時間がある、山に行きたい」という声も出てきた。会には、みんなで造り上げる定例山行や合宿には個人山行を入れないという原則があることから、「トレーニングも準備も、同じように進めていく」ことを明確にし、残雪の山だけでなく、違う登山志向、登山形態も合宿として位置づけることとし、現在のような「雪組」と「雪なし(花)組」の二つの登山志向の春合宿が行われるようになった。
合宿が終わって。一番好きな時間
このふたつの組の違いは、アルパイン志向かそうでないか、ということだけで、どちらが楽か厳しいか、どちらが上でどちらが下か、というものではないはずなので、どちらの組に参加するか、というのは会員個々が自由に選択すればいいのだが、私は会創立当初からやってきたことと、アルパイン志向の登山を渡していきたい、という思いがあるので、可能な限り、残雪期の山に向かう組にエントリーしてきた。
岳沢から奥明神沢を登って前穂高岳、槍沢を詰めて槍ヶ岳、涸沢をベースに北穂高岳、奥穂高岳、徳沢、横尾からの蝶ヶ岳往復や明神からの霞沢岳・・・春合宿で目指した山を何度も踏んだが、いつも、その締めくくりは一つの風景に集約された。
それは、使い終わった装備で膨らんだザックを肩に上高地へ下ると、あの残雪を踏むザクザクという靴底の感触や、周囲の白い世界はうそのように消えて、明るい春の日差しと新緑に移ろおうとする樹林を抜けて、河童橋の人ごみ、帝国ホテル、大正池、釜トンネルを抜けて上高地を後にし、沢渡から奈川戸ダムに沿って下流にさしかかると、広がるりんご畑の間にポツリポツリと現れる民家の軒先に鯉のぼりが泳ぐ青空と明るい陽差し、その明るさが次第に暖かさに変わっていく。私たちも3000mの雪の稜線から次第に標高を下げて、日常の生活へと帰っていく。車窓に広がる景色のうつりかわりを見るたびに、ああ、今年も春合宿が終わったなぁ、と思う、そんな景色だ。
この時間が、非日常の世界から街の中へ戻ってくるという実感があって、一番好きだったのだが、昨今はそれもかなわなくなった。
春(残雪期の)山の自然の変化
以前は、信州側の沢渡経由で上高地に入るのが普通だったが、安房トンネルの開通によって、昨今は平湯経由で岐阜県側から入山することが多くなった。また、近年は、積雪(残雪)が少なくなって、かつてのように、残雪期の山に身を置いても、それほど日常とは隔絶されたところへ登ってきたという実感があまり湧かなくなった。
厳しい気温や天候、多くの残雪の中へ入っていく登山者はもっと少なかったし、その人たちも私たちも、目標とする山頂を踏むために不可欠な雪上の行動技術や生活技術を学びながら、相当な緊張と、ある覚悟をもって入ったものだった。
気象条件も今ほど暖冬が続いて、降雪量も積雪量も少ない春山ではなかった。GWだというのに、北アルプス一帯は降雪、沢渡から上高地へ入るタクシーはチェーンを巻いて走ったこともあったし、別の年には、上高地は例年にない大雪で、明神や徳沢に向かう道の腋には背丈ほどの雪の壁が続き、横尾から涸沢や槍沢に入る分岐には、長野県警の救助隊員が立って登山者に注意を呼び掛けていたこともあったくらいだが、だんだんと、そんな光景も遠くなって、忘れ去られつつある。
残雪期の自然の厳しさや難しさが和らぎ(依然として存在し、時として牙を剝くのだが)、登山人口の広がりと、それに応えようとする商業主義的な流れは、登山環境に大きな変化をもたらしてきている。
コロナが山に与えたダメージ
更に、2020年からの爆発的な新型コロナウイルス感染のパンデミックは、登山者自身にも、山にも大きなダメージを与えた。
感染爆発により、移動の制限や、日常生活の当たり前だったことがなくなってしまったことで、一切の社会的活動や、日常の社会的結びつきはストップし、それは、登山の世界も例外ではなく、これまでずっと続けられてきた登山活動にも及んだ。この三年間、山岳会などの登山団体はもちろん、ガイド登山やツアー登山なども、休止もしくは不連続的な登山活動を余儀なくされ、春(もちろん冬山も)の積雪期の登山もまた、行動技術や生活技術を継承する機会を奪われ、それまで蓄積されてきた文化、その他諸々も含めて、途絶状態にあったといっても過言ではないだろう。それは、コロナ禍が少し緩んだかに見える四年目の今年に入っても、続いていると言える。
2020年は、ほとんどの山域の山小屋が休業した。移動の制限、感染力も死亡率も高い新型コロナウイルスを怖れて、移動はおろか、外出そのものが外的にも内的にも途絶え(山域によっては登山口に至るアプローチの道路を封鎖したところもあった)て、入山する登山者は激減した。
登山者数は2020年にはコロナ以前の3割、2021年は4割、2022年は6割まで落ち込んだと報告されている。
登山者の減少によって、山小屋は従業員の縮小を余儀なくされ、激減した登山者を迎え入れるための感染予防措置として、宿泊者数の制限、個別スペースの確保、小屋内部の施設の改良など、使用にあたっての新しい制約も求められるようになった。また、従業員減によって、それまで彼らの手弁当に頼っていた登山道の整備や修復に手が回らず、新しい問題が立ち現れてきている。
山小屋と同様に、幕営地もまた、管理上の問題から、設営できるテント数が制限された一方で、コロナウイルス感染予防を理由に、ソロテントが推奨され、パーソナルテントがテント場のスペースを占有し、しかも、前述のようなコロナ以前の行動技術、生活技術、文化が継承されないままに、巣ごもりから登山やキャンプをはじめた新しい登山者による、譲り合いや気配りや心配りなどに「気づかない」張り方が増えてきている。これからの登山を考えていく上での一つの課題といえるだろう。
テント場が山を決める
いま、会の春合宿の準備がすすめられているが、2022年の春山合宿は、徳沢をベースに蝶ヶ岳往復の計画だった。軒並み、ほとんどの山域の幕営場が使用禁止もしくは完全予約制になっており、計画段階で確保できる、あるいは予約不要のテント場を捜せば、積雪期登山のブランクのある参加メンバーが取り組める山も限られてくる、そういうプロセスで山域が設定された。
今年の春合宿の山域設定は、前年と異なる山域を挙げ、幕営の可否や状況を探ることになったが、当初挙がった唐松、白馬などのテント場への問い合わせたら、春は営業しない、幕営は禁止、といった返事だったらしい。「予約可」とあったのは、夏期のことで、テント場の整備や、トイレなどの整備ができず、そういう状況で勝手に使用された場合の、雪解け後の惨憺たるありさまが想定されるからか、禁止とは言わないまでも「来ないでほしい」というニュアンスだったという。
こうした条件の中で、残ったのが北アルプスの燕岳だったという経過がある。
時の経過
この大好きな季節を味わうことが「昨今はかなわなくなった」理由には、地球温暖化、コロナ禍による影響などを挙げたが、実は、もうひとつ、もっとも大きな理由がある。それは、時の経過だ。
自分(だけでなく仲間たちも)の身体の経年劣化と、思いの「ズレ」である。
かつて、合宿と言えば三泊四日、四泊、五泊という計画も珍しくなかった。短くても盛りだくさんの計画を消化して下ってくるのが当たり前のような時代があった。
今では槍なら槍だけ、蝶なら蝶だけを往復するという計画が普通だが、横尾をベースに、まず蝶ヶ岳を往復して足慣らし、その翌日は槍を日帰りで往復し、最終日は朝早くに横尾から上高地に戻ってくる、そんな春合宿ができたことが夢のようである。私自身も、仲間たちも若かったし、体力も気力も、現在とは格段の開きがあった。
伸びきったゴム紐のような筋肉と、軋む節々、寒さや冷たさに耐性がなくなり、原因のはっきりしない症状を抱えている体が、重い荷物や、長時間の行動、緊張を強いられるアタック、そういったトータルな残雪期の行動をだんだんと困難にし、この時期の山を遠いものにしつつある。
厳しい山行を終えて、暖かい陽光を潜り抜け、青空の下の、爽やかな田園風景から、日常の生活へと戻ってくるときの、充足感や達成感、そして安堵、開放感、といったものの象徴的なキーワードが鯉のぼりだったが、それは、かつて、仕事も子育ても現役だった頃の、山と自分との関わり方だったと言えるかもしれない。今の自分は、ずいぶん、そうした思いから離れてしまっている。充実感や達成感を味わうほどの山行に自分を向かわせることが難しい。非日常の登山を行うことにワクワクドキドキしている自分が、ちょっと離れたところにいる。
ひと月ほど前から、息子の飼っている雌のフレンチブルドッグを預かっていて、朝夕の散歩を夫婦で分担している。
「年喰ってる割に力、強いな。坂道なんか引っ張られると楽だけど…」
「9歳だから、もうおばあちゃんだよ」
「それほど年じゃないぞ。ドッグイヤーは人間の6倍か7倍だというから、人間ならまだ50代か60代、俺たちよりちょうどひと回りくらい若い勘定だぞ。会で言えば、〇Oさんや△△さんに引きずられて散歩しているみたいなもんだ」
会の仲間を犬と比較するのも失礼な話だが、重さや、突然走り出すときに引っ張る力や、スピードについていくのは結構大変である。ドッグイヤーで算出した彼女の年齢と私の年齢との差は、ちょうど一緒に山に登っている会の仲間たちとの年齢差と同じくらいである。カミさんも、会の仲間の顔ぶれと、犬に引かれて必死でついて行く私の姿を思い浮かべたらしく、大笑いだったが、日常の山行では笑いごとではなくなりかけている。以前は感じたことのない「歩けるか」という思いや、トレーニングをしてもなかなかそれが自分の今の体力にプラスになって返ってくることを実感できず、これをクリアすれば、あそこへは行けるかもしれない、などという考えが頭をよぎるようになっては、「通過点にすぎない」合宿が、目標になってしまって、トレーニングが「合宿に参加するため」のテストに成り下がっているようでは、あの大好きな時間に自分を置くことは難しいということなのだろう。今年の春合宿、私自身、体調に不安があって、参加を見合わせたが、無事に目的を果たして、笑顔で帰って来てほしいものだ。いい天気に恵まれますよう。
(2023.4.26)