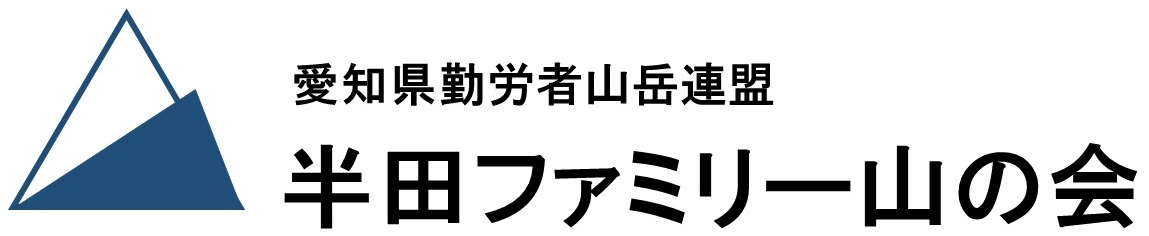洞井 孝雄
岸田総理が「広島に各国首脳が集まることに意味がある」とし、はなばなしく開催されたG7サミット。最終日にはウクライナのゼレンスキー大統領も参加し、G7の結束を演出しましたが、人類史上唯一の被爆国であるわが国の被爆地のひとつ広島で、その悲惨さを知ったはずの各国首脳が議論すべきは「核廃絶への道」であると思うのですが、かれらが行ったことは、被爆地から、核の使用を前提とする「核抑止力」を全面的に正当化し、自国の核兵器は肯定し、対立する国の核兵器を非難する発信をしただけだったということを、正確に見ておく必要があります。
6月の清掃登山が終わると、県連の遭対部の行事も、救急救命法講習会、無雪期救助訓練、確保技術講習会など講習会や訓練が目白押し。そろそろ会も夏山モードに切り替わって、夏山合宿の取り組みたけなわ。今月の「やぶマン」、ずばり「夏山合宿」を考えます。
コロナ禍のもとでの夏合宿は・・・
2020年に新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界中で、経済活動や社会活動をふくめて、「当たり前の日常」がなくなってしまう、という事態に陥った。
当然のことながら、登山の任意の団体である山岳会の活動もまた、さまざまな取り組みができなくなったり、中止せざるを得ない状況に直面した。一方で、こんな日常にこそ、文化、芸術、スポーツなどの取り組みが必要であることも実感された。
私たちの会では、会員の活動に制約を加えず、それぞれの職場や家庭環境に合わせて登山の取り組みをしよう、会の行事は、公的な団体としてこの時期に会として実施することが適切な取り組みであるかどうかはその都度判断しよう、ということをスタンスとした。
会員の中には、それぞれに置かれている環境や日常によって、仲間に対する過剰反応や「自粛警察」のような反応もあったが、定期的に運営委員会を開き、コロナの状況把握、会員の動向や会の方針の確認を行い、会員への周知、機関紙『もみのき』は休むことなく発行を続け、可能な限り、会活動を追求してきた。会の登山講座は、4月の開講予定を二度も延期したが、多数の受講者を迎えて実施された。
「合宿めざそう」という呼びかけ
会と会員たちの取り組みは、コロナ禍のもとでも追及されてきたが、山小屋のほぼ全面休業、テント場の閉鎖、移動の制約などによって、登山環境は著しく制限され、合宿もまた山域の条件により、実施そのものが見通せない状態が続いた。
私たちの会は、登山の基本や知識・技術などの多くを合宿で学んできた。
その合宿がまるッと一年もの間、組めないことは会員にとっても会にとっても大きなマイナスである、合宿そのものが何かということを知らない会員もこれから出て来るかも知れない、そんな思いに駆られて、2021年の夏前には、「夏合宿をめざしましょう!」という呼びかけを行った。
新型コロナ感染拡大の危険性はまだまだ続いていて、さまざまな制限が行われていて、入山上の制限や制約がまだ解けていない状態にあって、夏山合宿が実施できるかどうかは定かではないけれど、実施をめざすことで、打ち合わせや準備、トレーニング山行などを積み重ねていこう、そのプロセスを会員が共有できれば、合宿の意味や本来果たす役割を継承していくことができるだろうと考えたのだった。
一年間のブランクで、合宿の洗礼を受けられなかった仲間たち、前年、二回もの延期にも関わらず受講し、かつ講座終了後に入会してくれた仲間たちを含めて10数人が最初の夏合宿打ち合わせに参加し、そこから、合宿の意義と目的、任務分担、トレーニング山行など、本番実施が可能かどうかわからないけれど「本番目ざして」取り組みが始まった。
薬師岳。コロナ禍の功罪
エントリーした新しい会員が、アルプスをはじめとした主要山域の山小屋の営業状況、テント場事情を自主的にネットで調べてくれたことは、合宿の山域の設定に大きな力になった。検討の結果、2021年の夏山合宿の山域は北アルプス・薬師岳でおこなうことを想定し、それに向けて、打ち合わせで分担した任務について調べたことをレポートし合ったり、テーマ別に設定されたトレーニング山行に取り組むなどの準備が進められた。
想定された山域と日程が確認され、実施が現実味を帯びてくると、当初エントリーした仲間たちの中でも、実際の仕事や家庭の都合で参加できなる仲間たちも出てくる。
これまでであれば、自分自身が本番に参加できないことが明らかになった時点で、打ち合わせをはじめ、分担した任務の準備やトレーニング山行から本番参加できない仲間たちの足が遠のくのが常だったのだが、この「合宿をめざそう」という取り組みでは、本番直前まで、ほぼ全員がこれら準備の取り組みに参加し続けた。このことによって、合宿の取り組み、各任務の中身、その取り組みの必要性、トレーニング山行の組み立て、そうした一連の流れや、打ち合わせの中で出されてくるさまざまな疑問ややりとりまでも含めて、例年にも増して濃密な合宿の取り組みとなり、本来の「準備から下山まで共通の体験を通して学習と習熟の場とし、会の登山力量の向上を図る」と謳った合宿の目的の体現に近づくことができたように思う。コロナ禍の功罪のうちの数少ない「功」であったと言える。
本番では一泊二日のパーティーと二泊三日のパーティーが設定されたが、天候悪化の兆しもあって、全員が一泊二日の日程を終えたところで下山することになったが、出発直前の装備点検、テント生活や食事、その他諸々の場面での新旧会員の実体験ができたことは大きかったと思う。
2021年の冬合宿中止→雪山入門
その年の冬合宿は、前年実施できなかったこと、積雪が少なく十分な準備画できないこともあって中止とし、かわりに「雪山入門」の講座と実技を充てることで、ブランクを埋める取り組みを行った。
2022年春合宿。横尾~蝶ヶ岳
2022年の春合宿は、県連盟の加盟山岳会の多くが前年から合宿を中止したり、取り組む努力を放棄したりしている中で、合宿の位置づけと会の活動の中で何を勝ち取るかを明確にしつつ、8人で北アルプスの蝶ヶ岳に入った。
例年雪組と無雪組との二つのパーティーを組んで行う春合宿も、コロナ禍の下にあって、大がかりな取り組みは難しく、新人が多かったこと、テント場での制約もあって、初歩的な残雪期の山域一本に絞っての合宿となった。
2022年夏合宿 涸沢ベース。穂高へ
2022年の夏合宿は、前年の「めざそう」という呼びかけではなく、当初から「実施する」という呼びかけによる取り組みとなったが、北アルプスの入山事情は、まだまだ厳しく、山小屋やテント場の完全予約制がほとんど、という状況の中で、予約の不要なテント場として涸沢が挙がった。めざす山の候補のひとつとして、北穂高岳~涸沢岳~奥穂高岳が挙げられ、打ち合わせの中で目標の山域として確認されたが、コロナ以前の直近の夏合宿で、南岳~北穂高岳を縦走して下山した経過もあって、期せずして、北穂高岳につなげて穂高連峰縦走という形になった。
一年が経過して、初年度の恐怖は幾分薄らいだものの、コロナが相変わらず猛威を振るう中での夏合宿となった。
上高地、明神、徳沢、横尾と進むにつれて、登山者の姿は少なくなり、上高地から、先のところどころで、「感染者が出たので当面休業」という涸沢ヒュッテのお知らせが貼りだされていたり、徳沢の手前では、「クマよけ」の鐘が設置されていたりして、この二年間の山も大きく事情がかわってきているのだということを感じさせられた。
涸沢へ向かう登山者は、多くはなかったけれど、涸沢小屋は営業しているし、涸沢のテント場も開かれているので、皆無というわけではなかった。しかし、この時期のこの山域で、涸沢ヒュッテに人影がほとんどなく、テント場に設営されたテントもちらほらという状況は、半世紀近く通ってきた経験を手繰ってみても初めてのことだった。おかげで、北穂高岳から涸沢岳を越えて穂高岳山荘を巡るルートは、行きかう登山者も少なく、あおられることも渋滞もない、静かな縦走路を歩くことになり、その昔、登山を始めた頃の北アルプスの縦走路を思い出させた。
この取り組みもまた、前年と同じように、当初エントリーしたが参加できなくなった仲間が本番直前まで準備に加わり、「私たちの会の合宿本来の取り組み」になったように思う。早朝、わざわざ、献立の材料を渡すために集合場所まで来てくれた仲間たちもいたこともここで述べておこう。
合宿を支えるもの。位置づけ
昨年一昨年の私たちの会の合宿の取り組みを振り返ったのは、2020年以後のコロナ禍による活動の停滞やブランクがある中でも、合宿の灯を消さずに、取り組みを続ける努力がなされてきたことと、それが、何によって支えられてきたかということを言いたいからだ。
コロナ禍で多くの山岳会が、はやばやと合宿を「中止」した。
コロナ以前にも、県連の遭対担当者会議や合宿連絡・報告会議で指摘してきたことだが、ほとんどの山岳会の合宿計画書の「目的」欄には、「〇〇合宿」(笑)、「親睦を深める」「ピークハント」「リーダー養成」「〇〇を楽しむ」・・・などと記入されている。合宿の目的が「合宿を行うこと」というのは目的がないに等しいし、親睦は日常の会活動で深めることができないのか、と思うし、ピークハントはその山行のひとつの目的ではあるけれど、はたして合宿の目的か、とも思う。リーダー養成はそれらしく聞こえるけれどそうだろうか? 〇〇を楽しむ、に至っては、日常の山行と変わりがない。
ひっくり返して言えば、会としての「合宿」の位置づけや「合宿に取り組むことで、会として何をかちとるか」という命題がない、考えられていない、ということだろう。
そもそも、「合宿」の位置づけがないので、「行けるメンバーだけで」「いつもより長い日程がとれるので」「ちょっと足をのばそう」という計画がいくつか出てきて、それを「合宿」という言葉に置き換えて、計画書を出しているに過ぎない。
だから、コロナだ、移動制限だ、という話になれば、日常の山行計画の気楽さで、簡単に中止してしまう(ことができる)。
2021年の夏前に、県連の遭対担当者会議で、各会の合宿の取り組み状況を聞かれたことがある。「やりたいけれど見通しが立たない」「形になっていない」「中止」「いくつか計画しているパーティーはあるが・・・」という回答が出る中で、はっきりと会の方向性として「合宿をめざそう」という呼びかけをした、と報告したのは私たちの会だけだった。
コロナ以前にも他の山岳会に対して指摘してきたことは、計画書の目的を見ると、それぞれの山行の目的が書かれているだけで、会として何を合宿で課題にしているのかは書かれていない。いろんな山域に行くパーティーが集まって、会の合宿の意義や目的について話し合ったことも考えたこともないというのが本当のところではないか。
ただ行きたい山に行く、というだけなら、別に合宿でなくともいいということだ。
このコロナ禍の前後の合宿が中止されている間に、入会してきた新しい会員へのフォローや教育はどうしていくのか、これまでの「行ける」メンバーだけが計画して行く、そんな合宿では、新しい仲間は置いてけぼりを食らって、やがて合宿という言葉すら忘れられていくだろう。
本番が実施できるかどうか、不透明だけれど、「目指して」取り組むことはできる、合宿が会にとってどのような位置づけであり、どのように取り組んできたか、その取り組みのプロセスを一緒に体験することこそが、私たちの会の合宿の大きな意味であり意義でもある、そういう筋道を明確にしてきた経過があって初めて発想できる「呼びかけ」だったと思う。
かつて、会の合宿の打合せに集まった時に、最初に「意義と目的」について出し合おうとした際、「それがないとダメですか?」と言った会員がいた。
別の年には、「そんな話ばかりしていて、山域が決まらなければ先に進めないではないか」という声も挙がった。
繰り返しになるが、あの時に、そのことを曖昧にしていたら、多分、コロナ禍で軒並み合宿中止にしてしまって、知識・技術をつなぐことができなかった他の山岳会と同じ水準で肩を並べていたと思うのだ。
意義と目的を忘れず夏合宿を
2023年の春合宿本番は天候悪化のために、日帰りや割愛を余儀なくされたが、準備段階からの取り組みは、雪組、花組ともにエントリーメンバーみんなが手順を踏んだ取り組みをしてきたと思う。
ただ、実務面ではてきぱきと事が運ばれ、それなりに話されたことや決ったことが文書で確認されて進んだように見えるが、実際の運用面ではひとによって「やり方」「捉え方」が違って、その中身をすり合わせたり共通の認識にできたかどうかは「?」でもある(共通のものにする必要はないかも知れない。こういうやり方もある、ということを学べば)。終わりよければ・・・でもない。
これまで蓄積されてきたこと、経験、改善、その他諸々の筋道を学習、習熟するのが合宿だろう。
取り組みの基本は「意義と目的」、会員個々の思いはそれぞれでも、やはり会としての位置づけや意味をかみ砕いて理解し、どう具体化していくか、どう会員の血肉と会の力量に資するものにしていけるかを追求することが大事だと思う。
位置づけ、意義と目的を忘れず、豊かで、いつまでも会員みんなの中に残る夏山合宿が成功裏に行われることを期待している。
(2023.6.28)