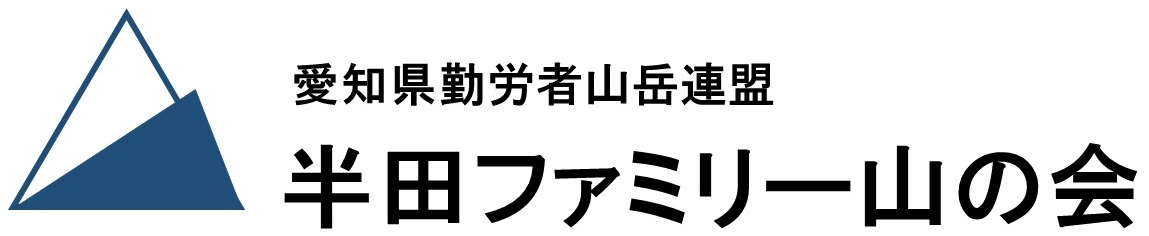洞井 孝雄
アメリカで開かれていたAPEC首脳会議が終わりました。ロシアのウクライナ侵攻については厳しく非難する一方で、イスラエルのガザ攻撃については「それぞれの立場を共有」としただけで言及しないという形だけの宣言が出されました。まさにダブルスタンダードなのですが、岸田さんは何をして、何を言ってきたのでしょう。
いま開かれている衆議院の予算委員会では、支持率過去最低の岸田内閣が野党側から様々な問題で追及を受けています。岸田首相にはまともに取り合う姿勢がありません。定額減税の原資がないのに「還元」だと言い、相次ぐ閣僚の辞任に「適材適所」と言い張る、パーティー収入の不記載問題、旧統一教会の被害者救済の法整備の不十分さ等々・・・。前後して、差別発言を繰り返す国会議員の居座り、オリンピック誘致を巡っての「官房機密費」の使途が取りざたされています。宝塚のいじめ自殺問題、子育てネグレクトや障碍者への暴行問題、大麻グミ、様々な事件や問題が枚挙にいとまがないほど報道されています。将棋の藤井くんが八冠達成、次いで竜王戦三連覇、八冠維持、大リーグの大谷くんがホームラン王、二度目のMVPで二度目の満票受賞、ほっとさせられるのはこんな話題でしょうか。
2023年も余すところ一カ月。
第42回入道ヶ岳記念登山も終わり、望年会や冬合宿の準備が始まっています。12月上旬に
予定されていた望年会は会場の都合で11月下旬に、例年、年末に実施されていた冬合宿は、昨今の降雪・積雪状況を考えて、年明け1月下旬に実施することになりました。
教育部が中心になって実施した岳習山行も無事終わったとのこと、雪の舞う中、長時間に
地図読みの実技だったようですが、何人かからはいい学習ができたという感想を聞いています。お疲れさま。
近いところでは、12月に予定されていた望年会が11月下旬に開かれることになりました。年内は、年明けの合宿をにらんでのトレーニング山行をはじめとして、「雪山入門」の実技や、さまざまな山行がいろいろ計画されているようです。まだ、本格的な雪があちこちに来ているという情報は聞こえてきませんが、雪山への準備や心構えはしておく必要があります。
思い出話も含めて、今回の「やぶマン」、冬山のあれこれを。
豪雪の年に
最近、同年代をさまざまな分野で彩った多くのひとたちが他界し、寂しくなる一方である。先日、俳優の天野静雄さんが亡くなったというニュースが流れた。
むかしの話だが、一度だけ、東海ラジオの「アマチンのラジオにおまかせ」という番組に呼ばれたことがあった。「冬山で遭難したらいくらかかるか?」ということについて話して欲しいということだった。年末から北アルプスに入っていた登山パーティーが、折からの豪雪で身動きが取れなくなり、あちこちでSOSを発信しているという報道がされていた年明け早々のことだ。
朝早くスタジオに入って、簡単な初対面の挨拶と雑談を交わした後、すぐに本番が始まった。台本があるのは彼らだけで、こちらはぶっつけ本番(まさに)。それでも別段、あがることもなく話ができたのは、天野さんの人柄だったのだろう。コマーシャルや曲が入って、マイクがOffになった時に「次、これ聞きますから…」程度のやりとりだけで、番組が進行していくのだが、面白い話題ではないし、遭難に関わることなので、いい加減なことは言えない。当然硬い話にならざるを得ないのだが、上手に合いの手を入れながらうまく会話として成り立たせていってくれたのは、やっぱりプロの仕事だった。
天野さんの番組に出たのは1990年代の豪雪の年で、番組の中で、「大雪で動けない登山者が救助を求めているという報道がされています。これからどうなっていくんでしょうか?」と聞かれ、「SOSを出している登山者たちがいま、どこにいるか、位置はわかっています。彼らの燃料と食料がどれくらい残っているかがカギでしょう。天候が回復するまで持ち堪えることができれば、すぐ救助されるだろう思います」と答えたのだったが、その日の新聞の夕刊には、天候が回復し、SOSを発していた登山パーティー全部がヘリで救助されたり、自力下山したというニュースが大きく載った。あたりまえのことだったが、言った通りの結果になったので、よく覚えている。天野さんのご冥福を祈ります。
実施は一月に
さて、今年は雪が遅く、少ないとの予報が出されている。先日、愛知県連盟の遭対担当者会議が開かれ、その席上で、各会の今年の冬合宿の取り組み状況を報告し合った。出席山岳会が少なかったが、ほとんどの会が、冬合宿を、年明けの1月に実施する計画だとのことだった。
私たちの会でも、第一回の冬合宿の打合せで、これまで慣例として年末に実施していた冬合宿を踏襲するかどうか、が話された。昨今の経過をみると、合宿の時期の降雪・積雪状況が不安定であるということと、合宿前に、会でやっておきたいトレーニングや冬山(雪山)の知識・技術の学習ができず、そのまま合宿本番という形になりつつあるので、それはまずいのではないか、きちんとプロセスを経て、合宿に繋げたい、そんな話になった。
冬山合宿が年末(年始)に実施されてきたのは、会社勤めのひとたちがまとまった休みを取りやすいのが年末年始であったこと、かつては12月から2月にかけての季節が厳冬期と呼ばれ、積雪も、降雪も冬期登山をおこなうのに十分な条件を備えていたことから、それが慣習になってきただけのことなので、年末年始に合宿を行わなければならない、とはどこにも決められていない。会の合宿として、きちんと位置付けられ、意義や目的に沿って取り組まれるのであれば、最適のコンディションで実施されるのが望ましい。会の中で、きちんと確認がなされれば、日程の変更も可能だ。第43期の半田ファミリーの冬山合宿は2024年1月に実施されることになった。年内の全会員対象の雪山入門のセミナーや実技も含めて、トレーニング山行の機会も増える。
冬期の分類、定義が変わってきた
この数年、私たちの会でも、年末の合宿の実施が迫るたびに、山域の選択に頭を悩ませていた。
前述したように、日本の冬山のシーズンの中でも、12月から2月までを厳冬期と呼び、積雪をはじめ気象条件の厳しさによって、登山者の行動を著しく阻害する条件が揃っている時期として分類されてきた。そうした気候のサイクルが、昨今の地球温暖化や暖冬によって、かなり大きく変化してきた。
身近な例で説明すると、鈴鹿スカイライン沿いに一ノ谷の駐車場がある。あの駐車場は、鈴鹿スカイラインが有料であったころの料金所の跡だが、それよりもっと前には一ノ谷付近にはスキー場があったことはほとんど知られていない。雪がなくなった。
藤原岳にもスキー場があったし、冬道がつけられる前には、雪崩で登山者が亡くなるほどの降雪、積雪があったのだ。
鈴鹿だけを見ても、年によって変動はあるにせよ、半世紀の間に、ずいぶん降雪も積雪も少なくなってきている。
県連の「氷雪技術講習会」は、数年前から本来の役割から似て非なるものに変質させられ(私は実質的に無くなったのだと思っているが)てしまったが、かつての氷雪技術講習会の山域は、富士山五合目で実施されていた。12月上旬、そこへ行けば積雪も、雪面の凍結もあたりまえのようにあって、講習や訓練の場として使えたからだ。
それが、直前になってドカ雪でスバルラインが閉鎖されたり、ある年には降らなかったり、で、いつの頃からか、講習の場を探さなければならない状況が増えてきた。中央アルプスの千畳敷や北アルプスの西穂高岳、時期をずらして御岳、さらには美濃の大日岳などに山域を変えながら実施してきたのだが、それらの山域も、昨今では、講習会実技本番直前にならなければ実施できるかどうかわからない、という積雪状況に変わってきている。
半世紀前には、北アルプスの山小屋などは、9月の声を聞けば冬支度が始まって、雪に閉ざされて翌年の春を待つ、ということが当たり前で、10月下旬から11月にかけては、標高の高い山域は、すでに限られたひとたちだけしか入ることのできないような世界だった。今のように、11月中旬になっても、北アルプスの山々が、紅葉の「見ごろ」として紹介されるようなことはなかった。環境、交通機関、施設、情報、その他諸々の整備が進んだことや、季節のボーダーがはっきりしなくなってきたこと、自然に向かう人たちの意識も大きく変化してきたこともあるが、やはり「雪が降らなくなった」こと、地球的に見れば「温暖化」が大きく影響しているのだろう。
実態に合わせる
これまで、冬山のシーズンに入る前に、冬山を始めようとする新人や会員たちが、雪山の洗礼を受けたり、氷雪技術のおさらいをしたりした後に、会の合宿や冬期登山本番に向かう、というサイクルが定番だった。ところが、近年は、山への降雪が遅くなり、積雪量も少なくなっているために、助走期間がないまま本番に入ってしまい、その後で氷雪技術講習の実技が行われる、という、順序が逆の状況が生まれてきている。
そうした状況を受けて、何年か前から、遭対担当者会議をはじめいろいろな場で、講習会、合宿、救助訓練などの日程を、実際の山の状況に合わせて見直すことの必要性を述べてきたが、なかなか形になって来なかった。本来なら、県連盟がそうした登山を取り巻く環境や登山者の動向をいち早く掴んで、実態に合わせて問題提起を行わなければならないと思うのだが、やはり腰が重い。今回のように、各山岳会が日程を先延ばしして合宿計画を組むのは、当然と言えば当然だし、県連盟の提起を待ってられない、ということでもある。
遭対担当者会議では、次年度以降の、冬山合宿遭対連絡会議、報告会議、積雪期救助訓練などの会議や行事の日程を実態に合わせて設定する、ということになった。
雪になった、雪があった・・・では
11月の中旬、鈴鹿の雨乞岳に登ってきた。山頂近くのところどころに、前日か前々日に舞った雪の名残が、かすかに残っていた。その数日前に、伊吹山が冠雪したというニュースが流れたので、多分、あの時にこの辺りにもチラチラと降ったのだろう。この数日後に行われた、会の地図読みの岳習山行でも、雪が舞ったとのことで、だんだんと、鈴鹿も雪に覆われる季節に向かっているようだ。
これから来年にかけても、いっぱい山行が計画されることと思うが、心配なのは、知識・技術・装備の裏付けなしに、山に入ったら「雪があった」「雪になった」という状況に出会うことである。
ずいぶん昔、12月の定例山行を鈴鹿で実施した時のこと。事前に提出された計画書を見ると、個人装備の中にピッケルもアイゼンも入っていない。その年も暖冬で、まだ積雪があるという情報はなかったが、沢沿いのルートを歩く計画だったので、担当の仲間に、アイゼンとピッケルを入れるように、という指摘をした。雪も降っていないのに・・・とかなりの抵抗があったが、押し切った。当日、積雪も降雪もなかったが、沢沿いの岩にはツルツル、てかてかの氷が貼り付き、スタート直後からアイゼンをつけ、ピッケルを使わなければ歩けなかったという経験もある。
秋に会の登山講座の実技を八ヶ岳の編笠山で実施した。押手川から青年小屋経由で山頂を踏んで下山する計画だった。
青年小屋までは、全く雪のない道だったのに、小屋から上部は、前日に降った雪で真っ白。雪の乗った岩に足をかけると、雪の下はつるつるの氷になっていた。
予期せぬ秋山のコンディションと、アイゼン、ピッケルなどを使わない季節を前提とした登山講座の実技では、これ以上の行動はできないということで、みんなで下山してきたこともあった。
古い例を挙げたが、二例とも、できる限り現地の直近の情報を把握することの必要性と、前者は万一を考えて準備すること、後者は山行の目的と状況に照らしてどう判断するか、ということを教えてくれた事例である。
冬山の学習、ブラッシュ・アップ
その入り口として、会の教育部が今年も「雪山入門」のセミナーと実技を計画してくれる予定になっている。雪山に入ろうという新しい会員は、積雪期と無雪期の山の違い、そこで必要になる知識と技術、装備について学習すること、すでに少しでも経験をして来た人は、もう一度それらをおさらいし、忘れかけていた知識・技術を思い出し、より確実なものにしていく機会だ。
今月号(12月号)の『山と溪谷』には、「雪山登山入門BOOK」という別冊付録がついていた。コースと装備の紹介、簡潔にまとめた雪山の歩行技術が写真入りで解説されている。山岳雑誌全盛の頃から、毎年、シーズンになると、繰り返し、積雪期の知識・技術について解説されてきた。いまは、ネットで検索したり、YOU-TUBEなんかの動画で、何でも調べることができるし、知識として知ることができる時代だ。ただ、技術や装備は変わるし、ネットの情報でも、本の情報でも、実際にやってみるとなかなか理解できているようで理解できていない、やれると思っていたのにできない、そんなことがいっぱいある。
しばらく大きな事故はあまり起きていないが、あちこちの近郊低山で事故が頻発している、というのが昨今の登山界の状況である。単独、我流の登山者が増えるにしたがって、こういう傾向はしばらく続きそうだ。何より心配なのは、こういう状況のまま、冬山に入っていくひとたちも増えるのではないか、雪が遅い、少ないと言われているので、余計に安易な入山者が増え、事故も増えるのではないか、ということだ。
山岳会の力
こんな時こそ山岳会が力を発揮できると私は思っている。山岳会の山行は、知識を蓄えたうえで、経験者と(つまり、会の仲間たちと)一緒に山に入り、知識を実践の中で、「ああ、こういうことだったのか」と、立体的に身につけることができる場である。
知っているひとは、何故、これが必要か、こうするのは何故か、ということも合わせて、初心者に伝え、自分の持っているものをより確実にする。初心者は、それらを現場で実際に学習しながら身につけていく。それができるのが、仲間がいる、ということだ。
ただし、新しい会員も古い会員も、「おそれをもって雪山に入ること」を忘れないことだ。
会の出番である。
(2023.11.29)