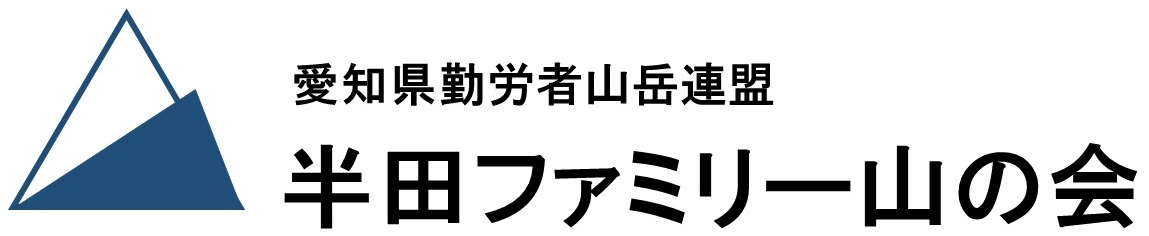洞井 孝雄
会の第44回定期総会が終わりました。新しい第44期の活動が始まっています。
総会では、活動の活発な割に、会の基本的な取り組みは不十分だったと言える、という総括がなされましたが、会員数63名に対して46名(73%)の仲間の出席があったことに、こうした指摘を克服して、さらに取り組みを進めることができる可能性を感じました。今年一年、みんなで力を合わせて、半田ファミリー山の会を大きく発展させたいものです。
「マイナス金利解除」、新聞紙上に大きな活字が躍りました。「賃金と物価が揃ってあがる好循環が強まった」という判断ですが、物価が高騰しているという実感はありますが、賃金の方はどうでしょうか? そして、預金金利やローンの行方は果たして・・・。一方で裏金問題は相変わらず、にもかかわらずそれとは別だ、という論理で憲法改正を進めようとする動きもあります。ロシアの大統領選挙ではプーチンが87%の得票で5選目。任期は6年だそうですから独裁政権として30年にわたる政権掌握はスターリンに並ぶとのこと。ウクライナ侵攻は終わりが見えません。アメリカの大統領選の行方も心配。またトランプが大統領に当選するようなことになったら、と思うとぞっとします。いろんな国で右傾化が進んだり、中国や北朝鮮の動きもますますキナ臭さを増しています。あっちでもこっちでも。それでも、声を挙げ続けましょう。
さて、今月の「やぶマン」です。先日、熊野古道を歩いてきました。去年歩いたカミーノよりも厳しい道のような気がしました。そこで少し考えたことを書いてみます。
計画を立てる作業が難しい
熊野古道は、大きく分けると、和歌山県の高野山から熊野本宮大社(小辺路)、奈良県の吉野山から熊野本宮大社(大峰奥駆道)、三重県の伊勢神宮内宮から熊野速玉大社、熊野本宮大社(伊勢路)と、中辺路と呼ばれる、紀伊田辺から熊野本宮大社~熊野那智大社、さらに熊野本宮大社~熊野速玉大社を結ぶ道がある。その中で最もポピュラーだといわれる中辺路(なかへち)の一部、滝尻王子から熊野本宮大社までを3月17日・18日の二日間で歩いてきた。往復のアプローチを入れると、都合四日間の旅となった。
何ヶ月か前から資料を見たり、ネットを検索したりして、熊野古道の概念を把握することから始めて、日程を決め、計画に落とし込もうとしたが、これが思うようにいかなかった。
2017年にフランスのサン・ジャン・ピエ・ド・ポーから、2018年にポルトガルのポルトから、2019年に再びサン・ジャン・ピエ・ド・ポーからサンティアゴ・デ・コンポステラまでを歩き、昨年6月から9月にかけて、フランスのル・ピュイからサンティアゴまでをつないで1600kmの巡礼路(以下、カミーノと表記)を歩いたが、回数を重ねるにつれて、現地の巡礼事情の変化や連絡手段の発達、訪れる人の増加などで、だんだんと宿舎の確保が難しくなってきているが、カミーノには、公営、私営の巡礼のための安価な宿泊施設が発達している。宿にあぶれた時は、巡礼のためのシェルターや、教会で野宿しても何とかやり過ごせる。
残念ながら、日本(熊野古道)にはそういう施設が多くはない。宿泊施設に泊まる費用も安くはない。野宿をする場所も限られているし、それらを許容する文化や環境もない。
宿の確保も問題
古道の左右前後、結節点になる町や集落の周囲にはいくつか民宿や一棟貸しのゲストハウスなどがあるが、ほとんどが小規模な宿で、カミーノのようなドミトリーやベッドとトイレ、シャワーだけ、という宿泊施設はない。キャパシティも絶対数も少なく、一年前から、あるいは半年、数カ月前から押さえられていて、予約が難しい。おおよその集落名や町の名前で、その付近の宿を検索して、予約可能な宿を見つけても、実際には歩く道から何十キロも離れた場所であったりする。現地の事情や勝手がわからないことも、計画を立てにくくする大きな要因である。
KUMANO KODOは海外で有名?
実際に歩いてみると、日本人より外国人の姿が多く、ひょっとすると、日本国内より海外の方がKUMANO KODOの名前はよく知られているのではないか、と思えるほどだ。
今回、歩いてみようと思うまで、熊野古道については、数年前に会の定例山行で登った便子山の入口の修復された石畳の一部と、四半世紀も前に白装束の行者姿で歩いた吉野から熊野までの大峯奥駈道(あれも熊野古道の一部だったのだな、と再認識した)くらいしか知らなかった。それが、昨年、カミーノを歩いていて、ニューヨークから来たという中国系アメリカ人と話していると、メモに「熊古」と書いて、これを知っているか? と差し出されて、ひょっとすると熊野古道か、と思い当たり、私たち以上に、海外ではよく知られているのではないかと気がついた。
初めてカミーノを歩いた時、行く先々で、一緒になった巡礼たちに、四国八十八か所巡りについて尋ねられたり、終点のサンティアゴ・デ・コンポステラの巡礼事務所内のツーリズム・オフィスのデスクの上に、八十八か所巡りのパンフレットが積まれていたのを見て驚いたことを思い出した。
私たちは、紀伊田辺からバスで、一般に古道中辺路のスタート地点とされている滝尻まで移動し、滝尻から二日間の古道歩きをしたのだったが、早朝の紀伊田辺のバス停にはすでにオーストラリアから来たという女性の5人パーティーがバスを待っていて、私たちを見ると気さくに声をかけてくる。今日から四日間の予定で歩くのだという。バスにも、道にも、外国人が非常に多く、日本人は数えるほど。大げさに言うと、KUMANO KODOでは、外国語がいたるところで飛び交っていた。
彼らには、事前に十分なツアー計画が立っているらしく、歩くコースもバスに乗る連絡も、宿もコンプリートの状態のように見受けられた。
途中で会った日本人の女性は、出発前に熊野本宮から熊野速玉大社へ向かう舟下りを予約しようとしたのに、いっぱいで取れなかったと話してくれたが、最終日、私たちが帰路に乗ったバスには多くの外国人が乗っており、そのほとんどが舟下りの出発点で降りて行ったのを実際に見たり、熊野本宮大社から宿に向かうバスを待っている私たちを尻目に、途中で知り合った外国人たちが、宿から来た車にピックアップされていくのを見ても、海外からの「巡礼」は、私たちよりもKUMANO KODOを熟知していて、動く術を駆使しているようであった。
実際に歩くと…
集落の中から舗装道路を歩いて、途中の標識に導かれて、山道に入っていく。石畳の道になったり、崩壊が進んで補修がなされている山腹の縁の道であったり、アップダウンが続いたり、急傾斜の登りになったり下りになったりする。登り終えると平坦な舗装道路に飛び出す。あれは、この登りの道のショートカットだったのか、いやいや、これが昔からの道で、舗装道路は車が山を越えるために新しく造られた道にすぎない、などと考えながら、重い足を運ぶ。
去年、ル・ピュイから歩いたとき、フランスでは、ここ以上に急なアップダウンが連続し、喘ぎながら山道を登りつめると、登り切ったところで舗装道路と出会って、目の前に民家があって車が停まっている、あれと同じじゃないか、と思ったり、フランスの、岩ゴロゴロの急な下りの道と、この熊野古道の石畳の下りとを比べたりしている。熊野古道の山道は、石畳の部分はごく一部で、それ以外はフランスほど荒れた道ではなく、ずいぶんよく踏まれて整備された土の道だ。
急な下りに黒っぽい石が敷かれた部分は、所によってはツルリとやりそうな傾斜と石で構成されていて、歩きにくい。ごつごつした石の上で、靴は様々な角度に振られ、窮屈な靴の中で痛めつけられた足先が当たって、悲鳴を上げる。
黒っぽいのは那智黒だろうか? これが崩れて、沢に落ち、河口に運ばれて、あの碁石の原料になるのではないか、などと思ったり、足元の大きな石は、何百年もの間に、多くの巡礼たちに踏まれ、すり減ってしまっているのだな、と思ったりする。
靴とワラジと石畳
靴底が少し滑ったりすると、昔のひとたちはワラジで歩いていたのだから、滑ることはなかったはずだ、石の道は、ワラジならフリクション抜群、足の裏はフレキシブルでクッション性もあるので、歩き易かったことだろう、沢登りでも、今のように渓流足袋とかウエディング・シューズとかにとって代わる前は、農業用地下足袋の上にワラジを着けて登っていたのだ。岩とワラジは相性がいい。熊野古道の石畳は当時のひとたちには歩き易い道だったんじゃないか、などと想像を逞しくしたりした。
車だとすぐなのに。なぜ歩く?
その一方で、平坦な舗装道路や、よく整備された道とミックスされたルートなのに、やはり平地を歩くのとは違う。車でせいぜい2時間足らずの距離を徒歩で何日もかけて、辛い思いをして、なぜ、移動しようとするのだろう、とそんなことを考える。
私は信仰を持っていないので、そのありがたさとか、御利益とかがどういうものかわからない。ただ、それぞれ曰く因縁とか、言い伝えとか歴史とか、建物やその周囲を取り巻く雰囲気の静謐さとか荘厳さとか、自分の感性に響いてくる「なにか」みたいなものの中に自分を置くことが嫌いではない。そのことは面白くて好ましい。
スペインのカミーノ歩きも同じで、あの国家的なスタンプラリーもしくは、国際的な集客装置(だと思っている)を歩くことは、相当に面白い。
それでも、さまざまな事物を見、日常とは異なる環境に身を置きながら、「どうして巡礼は、何十日もかけて荷物を背負い、足を痛めながらこの道を歩くのだろう、車でハイウエイをすっ飛ばせば、せいぜい一日の距離じゃないか、なんで?」と思ったのは、この熊野古道を、むかしから多くの老若男女、善男善女たちが蟻の行列のごとく熊野詣をしてきた、その有難みというのは一体何だったのだろう、と思うことと同じなのかもしれない。
歩いて何か得が?ご利益って・・・
カミさんに、「この道を歩いて、ゴールしたら御利益があるとか、何かいいことがあるとか、それがどういうことなのか、というのがわからないんだけど。あんた、何かそういうものがある、と思っとる?」と水を向けたら、
「私は、歩き終わった後に、ああ、今回も何事もなく歩けた、ありがたいなぁ、そう思うことはあるけど…」という返事が返ってきた。
「だけど、それは出かけてきて、歩いた結果でしょ? 出かけて来なきゃ、無事歩き通せたという結果もないわけだから。なんで、わざわざ、こんなえらい目をしに、出かけて来るのよ? ということが聞きたいわけだわ」
結局、答えは出ずじまい。
じゃあ、お前は何で歩きにきたんだ? と聞かれても、巡礼道を、手を合わせ乍ら歩いてきたひとたちの思いとはかけ離れた返事しかできないと思う。
私たちが出かけてくるのはスポーツであったり非日常をもとめるレクリエーションだと言ってしまえばそれまでだが、熊野古道にしてもカミーノにしても、いにしえに道を開いた人がいて、その後をトレースする人たちがいて、それが何世紀もの間、無数のひとたちによって踏まれ、広がり、今のような道になった、そのひとたちを動かしてきたものがなんなのか、が、知りたいのだけれど、わからない。
目的や理由は一人一人違う
四半世紀前(2000年)に、大峯の奥駈に参加した時に、その報告を『もみのき』と『岳人』に書いたことをふと思い出した。確か、あの中に、大先達の奥駈の意味というか捉え方、考え方についての話を書いた部分があった。書棚を探ると、果たして、『もみのき』№223(2000年8月30日)に、20ページほどの報告が載っていた。
その中の大先達の言葉を、長いが、引用すると、「この奥駈修行には、誰からも参加してくださいと頼まれてきた人はいません。自分で“行きたい”と言ってきた方たちばかりです。自分の力で歩くことが基本です。
-<略>- 一人で歩くというのは、一人で悶え苦しむということですが、人と一緒に歩くということは、その中で、自分のいやなところが見えてくるということです。どうか、そのいやなところや“我”を棄てる行をしてください。修験道は実験の宗教です。奥駈はこれ、と決まったかたちがあるわけではありません。奥駈のイメージはひとりひとり違います。 -<略> - みなさんなりの奥駈をなさってください。
-<略>- 歩いているときは、下界との縁を切って、余分なものをすべて捨てて行をしましょう」と、あった。
奥駈は、修験道の修行の形をとって縦走がおこなわれるので、他の熊野古道歩きとは少し趣が違うが、基本的には目的や意味、理由を、「何で?」と問いかけても、それは一人一人違う、ということに行きつく。多分、他の道を歩く人たちの御利益や有難さも、一人一人、抱えているものが違うように、得るものも違うはずである。
私が、講座などで「何故、山に登るか?」と言う問いかけをして、一人一人、それぞれ、山に登る理由もさまざまだし、山に登って何を感じるか、何を得るか、も違うので、答えに正解はない、と話していることと同じなのだろう。
なにも考えていなかった…
なぜ、えらい目をして、車ならすぐのところをわざわざ荷物を担いで歩くか、と考えてみると、一歩踏み出したあとは、歩くことだけに集中して、何も考えていないことに気づく。天気も、現在地も、時刻も、道間違いをしていないか、あとどれだけ歩かねばならないか、何処で休憩しようか、その他諸々、行動も思考も、すべてが歩くという行為に集約されて、下界での日常のあれこれを考える余地がなくなる、そんな状態に自分を置くことができるということだろう。多分、私たちの山登りも、そんなところに大きな理由があるように思う。
歩くときは必死で足を運んだので思考停止状態だったが、二日間を振り返ってみると、こんなことを考えていたのだった。
(2024.3.27)