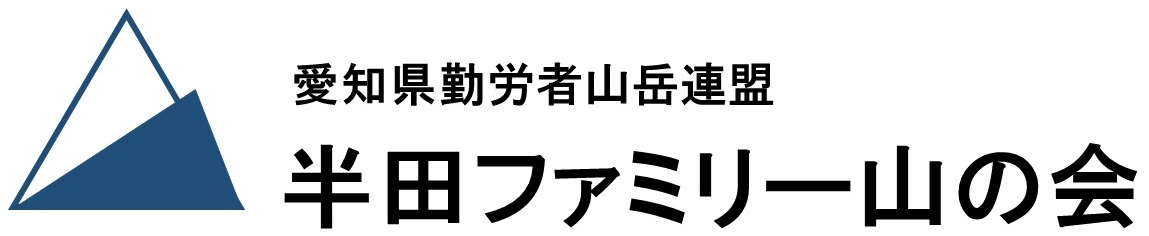洞井 孝雄
日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。被爆者たちが身を以てその現実を訴え続けてきたこと、もう一方では、この80年間、核による戦争はありませんでしたが、歴史の証人がだんだんと少なくなって、核の現実を認識しない世界の指導者たちが平気で核使用をちらつかせる時代になってきている、そのことへの危機感の表われであるとも受け止められます。世界に警鐘を鳴らす意味もあるでしょう。
広島選出の岸田前首相は、日本が人類唯一の被爆国であるにもかかわらず、核兵器禁止条約の署名・批准に背を向け、オブザーバ参加も拒否してきました。石破新首相は米国との核共有や地域への核持ち込みを検討する必要性に言及しています。ロシア、中国、イスラエル(事実上の核保有国とみなされている)、北朝鮮、イランなどの国々と同じく、核廃絶とはほど遠い道を歩もうとしているとしか思えません。私たちも声を挙げて行くことが大事ですね。
袴田さんの無罪判決が出され、検察側は控訴を断念して無罪が確定しました。証拠もねつ造であったことが明らかになりました。これに続いて、福井の中3女子生徒殺害事件の再審開始も決定しました。えん罪の恐ろしさを改めて思い知らされるとともに、数十年にわたって無実を訴え続けてきた人たちの地道な活動に頭が下がります。
米大統領選もひどい状況が伝えられています。結果が出るのが間近ですが、またまたトランプ前大統領が勢いを吹き返してきています。どちらに転んでも、課題は残りますが、あの嘘つきが再選されることだけは避けたいな、と思うと、ちょっと焦りを覚えます。
もうすぐメジャーリーグのワールドシリーズが始まりますね。ポストシーズンもリーグ優勝決定戦も、本当に強いチームばっかりでした。残るはワールドシリーズ、どちらが勝つでしょうか。大谷選手とジャッジ選手の対決が楽しみです。
9月から10月にかけては、天候が不順で、山行の中止や変更が相次ぎました。10月に入ると、紅葉の便りが聞こえてくる時期なのですが、まだ聞こえてきません。気温が高すぎるのでしょうか。それともタイトな選挙戦報道が忙しくて、そんな報道をする余裕もないのでしょうか。家の庭木が枯れ、こんな時期でもまだ蚊が飛んできます。
会では、記念登山の取り組みが着々と進められています。下見も終わって、どのコースが記念登山のコースに適切か、注意すべきポイントはどこか、など、きっちりと(?)抑えられているようです。今年も、山頂での豚汁サービスはありませんが、みんなで、会の大きなイベント、第43回の記念登山、成功させましょう。また、冬合宿の打ち合わせも始まりました。12月定例山行の山域も決まったようです。
さて、今月の「やぶマン」、この間の会の定例山行は、山域と天候に恵まれて、いい山行になっています。それだけにちょっと緩みも。「下見」の意味について考えてみましょう。
池ヶ谷道の講座実技は・・・
今月号の山行報告にも少し触れたが、鈴鹿での実技登山の山域を、現在のように鎌ヶ岳ではなく、入道ヶ岳でおこなっていた時期があった。毎年の入道ヶ岳記念登山では、椿大神社側から井戸谷を登って二本松尾根を下るのが定番だが、実技では、小岐須渓谷から池ヶ谷道を登り、滝ヶ谷道を下山するコースを実技の山域としていた。椿大神社側とは違って、下部には狭い登山道や鎖場があって、それを過ぎると、小さな流れに沿って上がる開けた谷や山頂直下で一気に広がる草原など、さまざまな表情をしていて、まず山登りを経験しよう、という実技には、いい山域だったからだ。
かつては、会員もよく登っていたルートだが、それがあまり、というかほとんど登られなくなったのは、登山道が荒れたことが大きい。加えて、春先から秋まで、それまであまり話題にならなかったヒルが多く出るようになったことも理由だろう。
前置きが長くなった。
しばらく前、会の登山講座の会場の準備や運営、実技の計画や実施を「教育部」中心でおこなった時期があった。その頃は、今のように春先ではなく秋に開かれており、実技では、池ヶ谷道から入道岳に登り、滝ヶ谷を下るコースを使っていた、
あるとき、例年のように、受講者と会員の参加者に計画書が配布され、装備や当日の注意事項など打ち合わせを行って、当日に臨んだ。池ヶ谷道から山頂までの登りは、前の週にやってきた台風のおかげで、枝や葉が登山道にたくさん落ちていたり、足元が滑りやすくなっていたりしたものの、それほどの変化はなかった。ところが、山頂から二本松尾根を下って、避難小屋下の分岐から滝ヶ谷道に入ったところで、問題が発生した。沢沿いの道がところどころ寸断され、流されてしまっている。
もしや、と言う胸騒ぎ。
「下見、した?」
当時の教育部長に尋ねると、
「してません」という、予想通りの返事。
急遽、会員の何人かを先行させ、徒渉できる箇所や山腹を巻ける箇所にロープを固定して、受講生を通すことで通過し、無事下山したものの、この年以後、実技の山域として使うことはなくなり、会員の足もこの山域から遠ざかった、と記憶する。
下見の定義
問題は、「下見」の話である。台風の後に下見もしないなんて、と言いたいわけではない。会の登山講座の実技の前には、それまで必ず下見を行っていた。下見をすることが、講座を主催する会の当然の責任だと認識されていたからだったのだが、手を離れた途端に、その認識がどこかに行ってしまったことだ。
なぜ、下見をしなければいけないのか? という点については様々に議論があるが、“一般の初心者に呼びかけて登山講座を開き、実技を行う”ということはどういうことなのか、を考えてみる。
会員がリーダーとして、一般の参加者とパーティーを組み、「山に連れて行く」という形態は一般的には「引率登山」と考えられる。
以下、『登山の法律学』(溝手康史著 東京新聞)からの引用だが、
引率登山の例として
①学校登山
②営利的な公募登山
③ガイド登山
④講習会
⑤危険回避能力のない初心者を連れた登山
が挙げられるとしている。
私たちの会の講座の実技は、④⑤に該当すると考えられる。
また、以下のようにも述べられている。
「成人の仲間同士の登山のほとんどは自主登山に該当しますが、しばしば参加者がリーダーに全面的に依存する形態の登山があります。しかし参加者とリーダーの関係にそのような依存関係があったとしても、原則として自主登山になります。成人であれば自分の責任において安全性を考えるべきであり、依存関係という事実状態によって法規範が左右されるべきではないからです。
人間は自然のメカニズムをすべて把握できないこと、人間はどこかでミスを犯す可能性があることから、本来、危険な登山は自主登山として行うべきであり、登山を引率して行うのであれば、比較的確実に安全管理ができる山域やルートを対象とすることが望ましいと思います。日本では、一般に自己責任が自覚されにくいので、引率登山で事故が起これば引率者に法的責任が生じる可能性が高くなります」
確実に安全管理ができるか?
持論を展開するのに都合のいい部分だけを取り出しているわけではなく、会の登山講座では、基本的に一般の初心者対象、経験者であっても初心者のつもりで、と断っているので、実技は「引率登山」と定義されるだろう。そこで、私たちが注意すべきなのは、「登山を引率して行うのであれば、比較的確実に安全管理ができる山域やルートを対象とすることが望ましい」ということである。そのためには、山域やルートを事前に熟知していることが必要になってくる。そのために前もって調べておくことが「下見」である。
実技の前に台風があって、当日出かけていったら道が崩落・寸断されていた、という事例は、絵に描いたようにわかりやすいが、台風があってもなくても、事前に現地の状況を把握して、「比較的確実に安全管理ができる」かどうかを知っていなければならない。このことがなされていなければ、事故が起きた場合には引率者に法的責任が生じる可能性が高くなる、ということでもある。会の取り組みとして、一般のひとたちに呼びかけをして山に連れて行く、ということは、こういうことでもある。
定例山行、下見は必要か?
私たちの会では、記念登山、清掃登山など、一般の参加者に呼びかける公開登山の場合に、こうした主催者の責任をどう果たすか、という点から必ず下見を行ってきた。
いつの頃からか、定例山行でも当たり前のように下見が行なわれるようになっているが、定例山行は山岳会の行事のひとつでもあり、成人の仲間同士の登山なので、引率登山ではなく自主登山の範疇に含まれる。溝手さんの本の引用の前半を読むと、それ(定例山行の下見)は、果たして必要か、当たり前か、という議論が出てこないわけではない。
私たちの会の定例山行は、日頃山行の機会がない会員にも、月一回は会として山行の機会を提供しよう、ということから始まっている。従って、行ける人たちだけの山域、山行ではなくて、会員みんなが参加できる山域・ルートを選んで、一緒に行こう、という性格の会の山行行事として位置づけられている。参加者を一般に広げた拡大版が清掃登山、記念登山である。が、ここで定例山行の下見は「不要!」と、主張するつもりも、否定するつもりもない。
昨今では、会員がローテーションで、定例山行の山域を提案して、実施に向けて呼びかけやとりまとめを行なってくれるようになってきている。担当を務めてくれる会員は、新旧や経験の多寡によって決められるわけではないので、候補に挙げた定例山行の山域を事前に把握して、ここならいける、という確信を得たいだろうし、自信を持って実施にこぎ着けたいという思いをもっているであろうことを考えれば、下見は会の山行行事の安全を担保するためにも、やっておいた方がいい、いややった方がいい、と思える。それもできるだけ実施する日程に近い事前に。
最近の事例、下見の意味と役割
となると、下見の意味や役割は明確である。
最近の定例山行では、二つある山頂を踏んで戻る計画になっていたのに、下見では手前の山頂だけしか踏まれておらず、その先の山頂までの道がどうなっているのかがわからなかった。地図をみれば、最初に踏んだ山頂から鞍部まで標高にしてどれくらい下って、どれだけ登り返せば向こうの山頂に着くかはわかるが、実際に下っていくと、傾斜や距離が加わって、途中で不安になった仲間も多い。これからどんなところが待っているのだろう、と、ドキドキハラハラワクワクできる舞台装置だと考えれば、それほど目くじらをたてるほどのことではないではないか、とも思うが、下見に来た以上、そのことを把握していて、仲間たちをそこへ誘うのと、自分たちも知らないまま、計画を立てるのとは違う、と思うのだ。AポイントからBポイントへ向かうという計画があって、その間の道はこんな風で問題なく行けるところだけれど、初めて行く人は途中で心配になってしまう部分でもある。でも、それは行ってからのお楽しみ、というのならOK、「行けるはずだけれど,Aから先は私たちもどうなっているのかわからない」というのではNGである。
本番で、下見に行っても、こことは違うコースを歩いたので、よくわからない、というのもNGで、下見にはなっていない。本番のコースも含めて歩いてみた中で、今回の山行はこのコースにしよう、とチョイスするのが下見の役目だろう。
パンデミックがようやく終わりに近くなった年の12月の定例山行を座佐の高という山域で実施した。家に籠っていた反動か、記念登山よりも多くの会員が参加した(ちょっと腹立たしかったが)定例山行だったのだけれど、日の短い12月の定例山行であること、登山口までのアプローチが長いことと、山域を周回するコースタイムも長いことを考えると、時間配分とタイムリミットを何時にどこまでで切るか、判断するかが悩ましい山域だった。
おまけに、下見に出かけて、途中で道を間違えて、計画していたコースも歩けなかったので、このまま会員を歩かせるわけにはいかない、と、急遽、その翌々日にもう一度、予定のコースを歩き、計画を立てたことがあった。二回、下見を行なったわけだが、このときほど、この山域での定例山行実施に賛成し、下見に参加する、と手を挙げたことを後悔したことはなかった。
当日は、天候にも恵まれたが、全員が無事、計画を消化した。タイム・リミットの時点で、続行の判断ができたのも、全体の行程とコースの概要を把握していて初めて可能になったことたった。
下見の責任!?
法的に責任があるか、道義的な責任があるか、というよりも、リーダーは「パーティーを安全に登らせ、確実に下山させる」責任を負っている。リーダーでなくとも、その山行を計画し実施に移そうとすれば、その山域を把握して、ここならこんなことができる、ここではこういう問題があるけれどこんな風に回避できる、トータルでみんなが安心して登って帰ってくることができる、そんな定例山行の下見をするとすれば、多分、本番よりも余分に歩き余分にポイントをチェックし、直近の状況による取捨選択を行なわなければならない、と思う。下見の負うべき責任である。下見の意味と役割をきちんと意識したいものだ。
(2024.10.30)