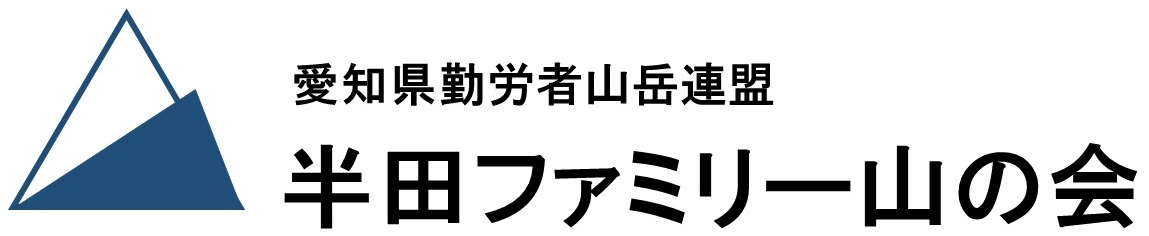洞井 孝雄
ビバーク。Webで探すと、「登山で露営すること。野宿」とあり、急激な天候変化などの緊急時にやむなく野営することとある。ドイツ語で「biwak」、フランス語で「bivouac」。日本語では「不時露営、不時泊」と表わされる。更にWikipediaでは、「しっかりしたテントを用いず(なかば外気にさらされるような状態で休息をとり、泊まる事)を指す用語」と説明されている。ひとつはフォアキャスト・ビバーク(forecast bivouac=計画通りのビバーク):あらかじめビバークする予定で行う。意図的に登山や探検を楽しむ手段、とある。
もうひとつはフォースト・ビバーク(forced bivouac=強制されたビバーク):予定通り行動できず、思いがけない場所で一夜を過ごす羽目に陥る、と説明されている。
前者は意図的に幕営具をツェルトやタープ、シュラフカバーなどに替えたり削ったりして軽量化を図るなど、沢登りや、少人数の縦走、アタックなどによく使われる。ここでは、不時露営と呼ばれる後者のビバークについて触れたい。
今年9月、マドリードで、バルセロナ行きの夜行バスに乗り損ねた。この日の便はもうない。午前1時半には、ターミナル内にいる人たちはすべて外へ追い出される。夜中にバスで移動する計画だったので、当然、宿泊施設の予約などはない。外に出て、30分ほども付近のビルや店舗、公園の間を歩き回って、やっと小さなビルの一階部分が小さな回廊のようになった乾いたスペースを見つけた。ザックの上に座り、半身を柱にもたせかけ、靴を脱いで腿の下に敷く。シュラフに入って足先をポリ袋に入れ、夜明け前の数時間をやり過ごした。
1982年の夏、グレポンの終了点から400mあまり、岩壁の懸垂下降を繰り返し、氷河に降り立つまであと100m、というところで時間切れになった。岩棚に腰かけ、ありったけのものを着込み、ザックに足を突っ込んで、背中合わせの相棒とレスキューシートを被った、足元の氷河の向こうのシャモニの街の明かりを見ながら、風と寒さの中で夜明けを待った。
1995年、マッターホルン山頂を踏み、下山を開始。ソルベイ小屋の上部で日没になった。テラスに確保用のロープを固定し、固まってツェルトを被った。仲間たちは岩の間に残っている雪や氷をメタクッカーで溶かしてコーヒーを淹れた。深夜、月の光が周囲の岩と私たちのいる一画を煌々と照らしていた。明け方には細かな雪が舞った。4000m附近でのビバーク。
2006年秋。懸垂下降中にロープに振られ、岩壁に右足を強打して骨折。尾根へ登り返し、翌日、救助のヘリにピックアップされるまでの一夜を過ごした南アルプス・鋸岳。
あまりホメられたことではない(そういう状況に陥った)が、私が経験した不時露営は4件もある。今年の例は都会での話だがフォースト・ビバークの定義に見事に当てはまってしまった。いずれも、早くスペースを見つけ、持っている装備をフルに使って、限られた中で最大限快適な状況を作って安全圏に入ることができて、ラッキーなビバークだった。体は痛いし、寒いし、辛いし、ビバークなどしないで済むに越したことはないが、慌てず対応できることが生き延びる方法のひとつである。早期に状況と条件を判断して、不足しているものを補うことができるのはそのひとの意思と体力、知識・技術だと思う。
登山に限らず、日常でもこういう場面に遭遇する可能性は高い。ビバーク(不時の状況に対応する)の知識と技術は学習しておくにこしたことはない。そんな風に思う昨今である。
(2023.10.25)