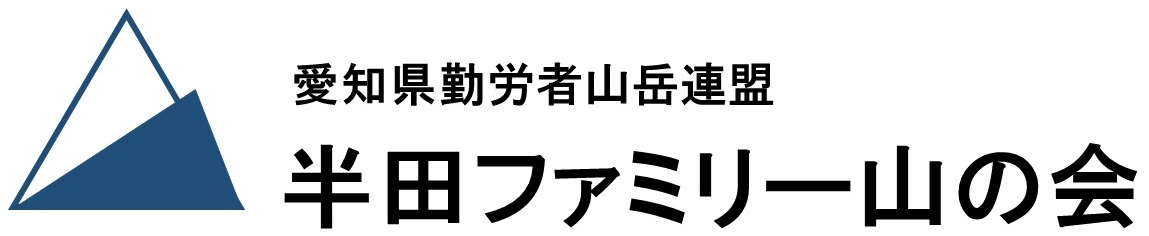洞井孝雄
ロシアのウクライナ攻撃の記事と、避難するウクライナの人たちの記事の報道が続いています。一般市民のロシア軍による殺戮の事実が明るみに出され、「戦争犯罪」の活字も新聞紙面に踊るようになりました。一刻も早く、戦争が終わることを願っています。
近郊の山では、真っ白な鳥が飛んでいるように見えるコブシが散り、ミツバツツジの鮮やかなピンク、その後のヤシオ、足元にはショウジョウバカマ、カタクリ、イワウチワなどが次々と入れ替わるようにして花を開いています。今年はシャクナゲが元気がありません。
会の登山講座はすでに一回目の実技を終えて、折り返しまで来ています。5月上旬に計画されている春合宿も、準備が進められています。トレーニング山行がなかなかできないことが心配ですが、無事、成功させたいものです。例年、6月第一日曜日に実施されていた鈴鹿山系清掃登山も、二年間、コロナで中止となってきましたが、今年は実施の予定だそうです。 今月の「やぶマン」、もうそろそろ、鈴鹿やその他の近郊の山々に出没し始め、話題になるヒル、それに関する本と、合宿の雪面を登るイメージをめぐっての話題について考えます。
ヒルは木から落ちてこない
メチャクチャ面白い本に出会いました。
すでに昨年9月に発行されていたのですが、自分のことで忙しくて、なかなか手を出せずにいました。たまたま、新聞の人物紹介のコラムに、この本をまとめることになった経過が述べられているのを読んで、すぐに手に入れました。ページをめくり始めたら、もう止まりません。結局、夕食後から就寝までの間に一気読みしてしまいました。
『ヒルは木から落ちてこない ぼくらのヤマビル研究記』(樋口大良+子どもヤマビル研究会 山と渓谷社)という本です。
三重県の元小学校の先生が、四日市市少年自然の家や藤原町自然博物館などを根城に地元の小中学生と子どもヤマビル研究会を立ち上げるところから話が始まります。子どもたちはヒルの観察をするなかで、さまざまな疑問を率直に出し合って、それを自分たちの力で解き明かしながら、ヒルの研究にのめり込んでいきます。そんな子どもたちを研究会に送り出したくせに、自分たちは触るのもいや、家に持ち帰って飼うなんてとんでもない、という親たちとのやりとりや矛盾した心理がなんともおかしい。山へは行きたいけれどヒルはイヤ、というウチの会員の多くにも共通した心理なんだろうな、とニヤリ。
研究材料のヒルを捕りに山の中へ入るところから、話は始まるのですが、その舞台が入道岳であったり、藤原岳であったり、身近な山域であることもよけい私たちの関心を惹きます。ヒルに噛まれても無害であること、ヒルは何に引き寄せられて出てくるのか、何度から何度の間で活動するのか、塩分に弱いと言われているが、どれくらいの濃度まで活動できるのか…日ごろ、私たちが、山でヒルに食われて、あれこれ言われていることや俗説のひとつひとつが、本当かどうか、実験をとおして、解明されたりひっくり返されたりして行きます。とりわけ、書名の「ヒルは木から落ちてこない」ことを、自分たちの実験を通して証明するくだりは圧巻。自分たちの身体で実験してわかったことを、いろいろな場所で報告するのですが、古くから言われてきたことを信じているおとなたちの固い頭はなかなか受けつけず、信じようとしません。そのやりとりもたいへんに面白い。また、どんなところにヒルは出るのか、どうやってヒルが運ばれるのか、目にした事実から仮説を立てて解き明かそうとしていくプロセスを読み進むと、ああ、やっぱりそうだったのか、いやあ、てっきりこうだと思い込んでいたけど違うんだな、とか、あ、そういうことだったのか、など、私たちが、これまでヒルについて知っていたことも、曖昧なままだったことも、ヒル研の子どもたちの実験でひとつずつ確かなものに変わっていく楽しさや新しいことを知る嬉しさで、久しぶりに、推理小説の謎解きに匹敵するようなワクワク感を覚えた読書をしました。ちむどんどん、というやつでしょうか。
私たち山登りをする登山者としては、ヒルはできれば避けたいもののひとつですが、やみくもにヒルを嫌がったり怖がったり、気味悪がったり、大騒ぎする仲間たちがけっこういるのですが、血を吸われて気味が悪いのはわからないわけではないけれど、やかましいなあ、と思うこともたびたび。いったいどれくらいほんとのことを知っていて騒いでいるんだろうか、とも思ったり。そんな時に、この本は”ヒルの真実”というやつをきちんと私たちに教えてくれます。
もうひとつ、気付いたことがあります。このヒル研の子どもたちは、毎年名古屋市内でひらかれる「登山フェス」のブースでも何年か前から研究したことを報告してくれているそうですが、そういう話がちっとも私たちの耳に届いて来ない、ヒルだヒルだ、と騒いでいる会員からも、こうした情報や知識が伝わってこない、ということは、なかなか、そういう外での催しものに顔を出したり、外からの情報を吸収したりすることのないままに、ヒルが出そうな季節には、その山域には行かない、と決めているだけで、未だに俗説の世界にいて、ただ毛嫌いしているだけのような人が多いんじゃないか、ということでした。そういう人たちに読んで欲しい本です。
合宿遭対連絡会議で…
先日、県連盟の春山合宿遭対連絡会議が開かれました。私たちの会も、今期は春合宿を実施するので、計画書を持参して会議に出席しましたが、多くの会はまだコロナ禍のもとにおかれているようで、計画書を持参した山岳会は数えるほどでした。
その中で、ある会の北アルプスに入るパーティーの計画書に質問と指摘が集中しました。
もう、何度同じ話になったことか、わからないのですが、持参するザイル(ロープ)の太さと長さと本数の話です。
私たちが岩登りを始めた時の通常の登攀用ナイロンロープの太さ(径)は11ミリ、長さは40mのものをシングルで、あるいは径9㎜、長さ40mのものをダブルで使用するというのが一般的でした。ロープをいっぱいに伸ばした長さで、確保をしながら登っていくのですが、このロープ一本分の長さを1ピッチとして、壁の長さ高さを数える目安としています。
最近のロープは、だんだんと強度を増し、径も細くなって、一本の長さも長くなってくる傾向にあります。
以前の私たちの9ミリの径のロープは8.2ミリまで細くなり(それだけ軽くなるわけですが、かわりに)50m、60mという長さに変わってきました。登る対象としての岩場や壁が、時代と、登り方の変化とともに変わってきたということかも知れません。ですが、まだ8ミリ以下の径のナイロンロープとなると、それにメインの体重や荷物などの荷重をかけて十分に耐える強度を持ってはおらず、あくまで「補助」の範囲内にしかすぎません。
私たちの会のベーシック・ミニマムの中に、共同装備のベーシックとして「細引き」(8ミリ×20m)が入っていますが、これも登攀用ではなくて、万一の際の補助、確保用として携行する者としての位置づけです。基本的には、じわりと荷重をかける(静荷重)使い方で、急激にある高さから重量物が落下することによって一点に負荷が集中する(衝撃荷重)という使い方を想定していないので、8ミリという太さの軽い「細引き」を持って行こう、ということに決めているわけです。
ロープの太さ、長さ、本数
説明が長くなりました。本題に戻します。
ある会から、奥穂高岳と北穂高岳に登る7人パーティー(A)、北穂高岳に登る7人パーティー(B)の二つのパーティ―の計画書が出されました。Aは8.5ミリ50mのロープ1本、Bは8.0ミリ30mのロープ2本、を携行する旨の記載がありました。
春の残(積)雪期の北アルプス、奥穂、北穂というのは、涸沢をベースに登山者でにぎわうところで、誰もが憧れ、多くの登山者がおしかけるところですが、今も昔もやはり厳しい山であることに変わりはありません。
年によって違いますが、奥穂高岳へは穂高岳山荘間、山荘からハシゴ場を越えて稜線までの間で、ひょっとしたらロープを使う必要のある場面が出てきます。
Aパーティーの8.5ミリ50mロープは、しっかりとリード、確保ができるメンバーと他のメンバーがロープ処理に長けていれば、一本でことたりるでしょう。下りも気を抜かずに確保しながら下降して欲しいものです。ベースまでの行程でも過去、滑落事故や雪崩事故が起きていますのでご用心、ご用心、というところです。
問題になったのは、A、Bとも、北穂高岳に登るときの装備として、それぞれ7人パーティーで、8.5ミリ50メートル1本、8ミリ30メートル2本と書かれていますが、これでいいのか? ということでした。
この時期、北穂高岳に登るのには、北穂沢を使います。涸沢から北穂高岳小屋に突き上げている北穂沢がこの季節には長大な雪の斜面になります。奥穂と同じように、年によって状況が違いますが、数百メートル続く急峻な雪の斜面は下から上までほとんど平たんな部分はありません。休憩するような場所もないので、雪面にバケツを掘って(雪面を蹴り込んで雪を掘り、バケツほどの足場を作ること)一休みする以外は、アイゼンとピッケルを雪面に効かせて、登り続けるしかありません。
やっと登り切ったあとは、下降が待っています。登りと違って、急斜面の下降は、あまり経験がなかったり、緊張しているひとにとっては一歩、下に向かって足を踏み出すときにはこわいものです。また、状況によっては、ロープで確保しなければならない場面も出てきます。
確保と下降のイメージ
ロープをつけたメンバーが先行して、ロープの長さいっぱいまで下り、このメンバーを上で他のメンバーが確保します。他のメンバーは上下に張られたロープにプルージックなどの巻き付け結びをかけ、自分のハーネスとつないで命綱として下って行きますが、パーティーの人数が多い場合は、順次降りたメンバーが溜まってしまって、全員が下り終えるまでどうしているか、ということが課題になります。全員つながったままの状態で、上で確保しているメンバーが、確保支点を解除し、下ってくるのを待っている間は、ロープ回収はできません。平たんな場所のない、ロープで確保されながら下っているような斜面で、確保を外して立って待っている、ということには無理があります。別に確保の仕掛けを設けるためには、もう一本ロープが欲しい、ということになります。
一人が上で確保し、一人がもう一本のロープを担いで下って、もう一本のロープをで、それ以後に下ってくるメンバーたちが下で滑落することのないよう、確保支点を作るか、一本目のロープの下端を固定し、その確保支点からもう一本のロープを下に伸ばして、他のメンバーを下らせている間に上のロープを回収する、と言った形での動きが必要になってきます。
以前、10人のパーティ―で、一本しかロープを携行しなかった例で、上で一人が確保し、一人がロープを伸ばし、三番名に下ったメンバーが、下でプルージックを外して、他のメンバーが下降するのを待っている間に、足元の雪面が崩れて、400mほど滑落する、という事例がありました。9人が下降し終えるまで、張られた一本のロープは回収できず、下ったメンバーたちは、ロープの下端で、プルージックを外して不安定な雪の斜面に立って待っている、という状況だったわけです。最初の1~2ピッチのロープ確保だけで、普通は自力でそのまま斜面を下って行けるようでなければ、この斜面の下降は難しいのですが、やはり、メンバーの数が多い場合には、複数のロープの準備が必要だと思います。
さらに、Bのパーティ―の場合には、8ミリ径の30mロープ二本となっていました。複数携行するのは大事なことですが、問題はその太さと長さです。8ミリというのは、前述したように、登攀用ロープでシングル使用には十分耐える強度の太さとは現時点で考えられません。同時に、径が細くなればなるほど、手袋をはめての積雪期の使用では握っても止まりにくく止めにくくなります。ほんとうに、ロープの強度を理解し、使い方を想定しているのか、と心配になりました。合わせて、30mという長さです。北穂沢の雪の斜面の長さ大きさを知っていて、そこでの最悪の場面をきちんとイメージできているかどうかが気になりました。
他の会のメンバーから。ロープの太さと、長さについて質問と、もっと長いものにしたらどうか、という指摘がありました。もう一つの会のメンバーからは、自分たちが登った時に一本しかロープを持参しなかったことへの反省が述べられました。
同時に、Bはスノーバー2本を携行する記載がありましたが、Aには記載がありません。このことで、他の会から、雪上で他のメンバーを確保する際にどうするのか? と聞かれると、「スタンディングアックスビレイで確保します」と答え、「その際に、自己確保はどうするのか? スノーバーを使って支点をつくらないのか?」と重ねて聞かれた質問には、「他のメンバーのピッケルを使って…」という答え。そうすると、ピッケルを確保支点として貸したメンバーは、ピッケルなしで雪面を下降することになるのですが……どうやらそういう局面での経験はなさそうです。頭では理解していても、実際にどうするか、というと、なかなかイメージすることは難しそうです。想像力、というより経験の不足かも知れません。
終わりに
今回指摘を受けたパーティーのメンバーの中で、A、Bとも、この季節の北穂に登ったことのあるメンバーは一人か二人、ということでした。数少ない経験者は、そういった困難さや問題を指摘し(でき)なかったのでしょうか。この計画や受け答えを聞いていたかぎりでは、リーダーとして、仲間をリードした経験をもったひとがいたようには思われません。同じ会には、この斜面で、他の登山者が滑落してきて負傷した経験や、尾根上で停滞、ビバークを余儀なくされる経験をした「先輩がた」が結構いるんだけど、なぁ。
いずれにせよ、この二年間に確実に経験者の数が減り、実際に山のイメージを以って計画を立てられるひとが少なくなったことを実感しています。このブランクはいつ埋まるのでしょう? ご注意!! (2022年4月)